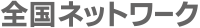法的手続
5 証拠収集
自分自身または家族などが脳心臓疾患ないし精神疾患を発症した場合、その原因が過重労働によるものと言えるかどうか(上記2.~4.で述べた労災認定基準に該当するかどうか)を判断するためには、業務の負担がどの程度であったかを示す証拠を収集する必要があります。
どのようなものが業務上の負担を判断する証拠になるかについては、例えば、長時間労働に関する証拠としては、「タイムカード」や「業務日報」などの労働時間を記録したもののほか、業務用のパソコンから送信した「業務メールの送信日時」、業務を始めるときにパソコンを立ち上げた「ログイン記録」と業務終了時にパソコンをシャットダウンした「ログオフ記録」、オフィスを退出した時間がわかる「セキュリティ記録」、さらには、家族に対して送信した「これから帰宅するとの報告メールの時間」、「本人の日記」なども重要な資料になります。
また、業務上のストレスの証拠としては、例えば、「上司からの叱責メール」、「健康診断の面談記録」、医療機関を受診していた場合には「病院のカルテ」、業務上の事故を起こしていた場合は「事故報告書」、さらには職場の同僚からの聞き取りなども重要になります。
これら証拠をどのように集めるかは、その労働者の職場や立場などによっても変わってきますが、まず自分自身や家族が保有しているものは、しっかりと保存をしておくことが必要になります。会社が保有している資料については、会社に対して直接開示の依頼を行うほか、会社が証拠隠しや改ざんを行うことが疑われる場合には裁判所を通じた「証拠保全手続」(当日に裁判官とともに会社を訪れ、資料を提出させる手続)を取ることもあります。
どのような手続を取るかは、各事情を総合的に考慮して判断することになります。
6 労災申請
上記5.の証拠収集を経て、脳心臓疾患や精神疾患の発症の原因が過重労働によるものと疑われる場合には、勤務していた事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に労災申請を行うことになります。
労災申請は、疾患を発症した被災者本人かそのご遺族(被災者の収入によって生計を維持していた配偶者等)に認められています。
労災申請を行ってから結論が出るまでの期間は、おおむね6か月から1年程度の期間を要するのが実態となっています。労働基準監督署は、申請を受けると、その期間に、労災申請時に申請者が提出した資料に加え、会社に対して資料提出を求めるほか、被災者やその家族、会社の関係者からも聞き取りを行い、様々な情報を集めた上で、疾患の発症が業務を原因とするものかどうかを判断することになります。
労働基準監督署の調査の結果、労災と認められた場合には、被災者本人は治療を受けるための療養補償給付や疾患により働けないときの休業補償給付(障害を負った場合には障害補償給付等も)を受け取ることができ、被災者が亡くなっている場合には、ご遺族は遺族補償年金や遺族補償一時金を受け取ることができます。
ただし、療養補償給付と休業補償給付の申請の時効は2年、遺族補償給付の時効は5年などとされている(絶対ではありません)ので、申請の時期については注意をしてください。
なお、会社が申請に協力してくれなかったり会社が労災保険料を支払っていなくても労災申請が可能であること、取締役などであっても労災申請が可能であること、退職後の発症でも労災の対象になることなど、申請を諦めなくてよい注意点なども多く存在するため、申請を検討される場合には、諦めてしまう前に専門家へのご相談をお勧め致します。
7 行政不服申立て
労災申請が認められなかったという場合であっても、それで終わりというわけではありません。労基署の判断を見直すよう、行政に対して不服申立てをすることができます。
まず、各都道府県労働局に対し、審査請求をすることができます。これは、労基署の決定を知った日の翌日から3か月に行うことが必要です。なお、審査官の決定前であっても、審査請求をした日から3か月が経過しても決定がない場合には、決定を待たずに再審査請求又は訴訟を提起することができます。
仮に審査請求での結果にも不服があるという場合には、労働保険審査会に対し再審査請求を行うことができます。これは、審査請求棄却決定書の謄本が送達された日の翌日から2か月以内に行うことが必要です。
労働保険審査会での結果にも不服があるという場合には、裁判所に提訴し、労基署の決定を取り消すことを求めることができます。提訴は、再審査請求棄却の裁決を知った日の翌日から6か月以内に行う必要があります。
以上を図式化すると、下記のようになります。
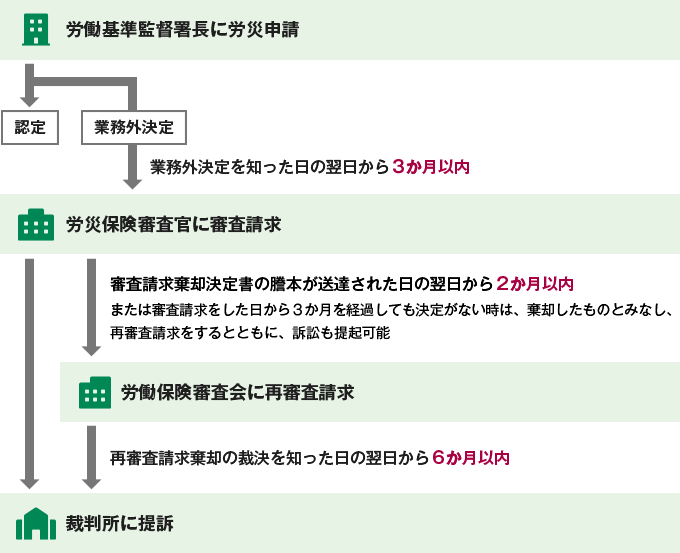
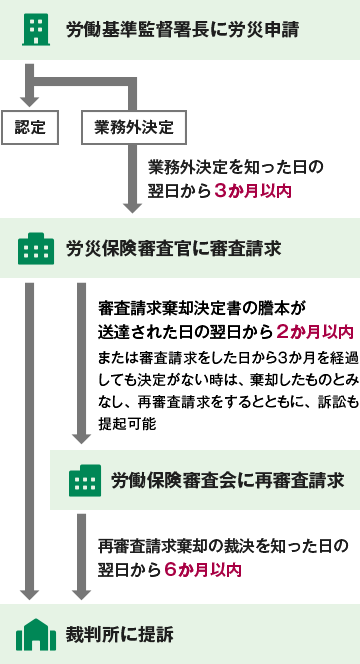
労基署長に請求 ↓ 業務外決定を知った日の翌日から3か月以内 労災保険審査官に審査請求 審査請求棄却決定書の謄本が送達された日の翌日から2か月以内(または審査請求をした日から3か月を経過しても決定がない時は、棄却したものとみなし、再審査請求をするとともに、訴訟も提起可能) 労働保険審査会に再審査請求 再審査請求棄却の裁決を知った日の翌日から6か月以内 裁判所に提訴
8 労災行政訴訟
1 行政訴訟の手続き
- 労災 の分野で「行政訴訟」とは,行政(労基署)が行った「遺族補償給付等不支給処分」の取消しを求める訴訟を指すのが通常です。不支給処分を取り消すという裁判所の判決が確定すれば,行政は確定判決に従い,不支給処分を取り消した上で,支給決定を行うことになります。
- 行政訴訟は,労基署が不支給処分を行ってもすぐに起こせるわけではありません。不支給処分に対する審査請求を労働者災害補償保険審査官に対して行い,①審査請求が棄却されたとき,②審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないとき(審査請求が棄却されたとみなすことができる),に地方裁判所に訴訟を起こすことができます(労働者災害補償保険法38条2項,40条)。
- この不服申立て手続については,平成28年4月1日施行の法改正がありました。旧法では,審査請求の後,再審査請求を労働保険審査会に対して行った上でないと提訴ができませんでした。法改正により,以前より早い段階で行政訴訟を起こすことができるようになりました。
- なお,新法のもとでも,審査官によって審査請求が棄却された後,直ちに行政訴訟を起こさずに,労働保険審査会に再審査請求を行うこともできます。再審査請求をすると,労基署等が収集した資料が冊子の形で被災者側に開示されますので,証拠収集のために再審査請求の手続を利用した上で行政訴訟を起こすことも考えられます。
- 行政訴訟では,通常の民事訴訟と異なり,裁判所での和解による解決はほとんど行われていません。行政(国)が和解に応じないためです。そのためもあり,行政訴訟の提訴から1審判決までの期間は,証人尋問を行う事件の場合,平均で約2年間程度を要しているのが実情です。
- 行政内部の不服申立て手続である審査請求や再審査請求では,労基署の不支給処分が取り消される割合は少ないのが現実ですが,行政訴訟では,行政の認定基準とは異なる判断基準で審理することもあり,労基署の不支給処分が取り消される割合も,決して少なくありません。平成12年の最高裁判決以後,脳・心臓疾患や精神障害・過労自殺の事案で,労基署の不支給処分を取り消して原告側が勝訴するケースが増えてきています。
2 行政訴訟での判断基準
- 労基署など行政機関の判断は,厚労省の認定基準に拘束されますが,認定基準は行政内部の通達に過ぎませんので,裁判所は認定基準に拘束されません。裁判所でも,認定基準は参考にはしますが,形式的に認定基準にあてはめると業務外となる事案でも,裁判所では総合判断により業務上と認定されることがあります。
- 判例は,業務上の災害であるというためには,業務と疾病との間に相当因果関係のあることが必要であるという立場を取っています(最二小判昭和51年11月12日)。
そして,脳・心臓疾患による過労死の場合には,被災者が過重な業務を遂行したことにより,被災者の有していた基礎疾患がその自然の経過を超えて悪化し,脳・心臓疾患を発症したと認められる場合に業務起因性を認めるとしています(最三小判平成16年9月7日等)。 - 精神 障害・過労自殺事案の場合には,厚労省の認定基準では,心理的負荷の強度が「中」の出来事が複数重なっても,総合評価が「強」とされるにはハードルが高いなど,複数の出来事を総合的に評価する視点が弱いといえます。これに対し,裁判所では,心理的負荷をもたらす業務上の出来事が複数重なっていることを総合的に評価することに積極的な傾向があります(東京地判平成23年3月2日等)。
また,認定基準では,精神障害を発症した後,自殺に至るまでの症状悪化時の出来事は重視しませんが,裁判例の多数は,発病前のみならず,発病後自殺に至るまでの症状悪化時の業務上の出来事による心理的負荷も総合的に評価しています。 - 行政段階では,業務起因性の判断について,時間外労働時間数のみが重視され,業務の質的過重性の評価が軽視されがちな傾向があります。一方,裁判所は,労働者の勤務実態に基づき,業務の量的過重性及び質的過重性を総合的に評価する立場を取っています。そのため,時間外労働時間数が認定基準を満たしていなくとも,業務の質的な過重性を総合評価して業務起因性を認めた裁判例も多数出ています。
- 厚労省の認定基準は,被災者の「同僚労働者」や「同種の労働者」にとって過重な業務だったかを判断基準としていますが,裁判所は必ずしもそうではなく,通常想定される範囲の同種労働者(基礎疾患や一定の脆弱性を有するものの,日常業務を支障なく遂行できる労働者を含む)にとって過重な業務だったかを判断基準としています。
- 厚労省の認定基準では,原則として発病前おおむね6か月間の業務上の出来事を評価の対象にしていますが,裁判所は,発病前6か月~1年半程度の業務上の出来事も,被災者が主張すれば評価の対象にすることがあります。
3 行政訴訟の進め方
- 行政訴訟では,認定基準に形式的にとらわれることなく,被災者の具体的な勤務実態を個別に立証し,総合的に業務の過重性を明らかにしていくことが必要です。
- そのためには,行政段階で収集した証拠の分析を行い,足りない部分については,新たな証拠の収集に努める必要があります。
- 案件によっては,業務と死亡との因果関係を立証するために,医師に相談し,意見書の作成や裁判所での証言を依頼することが必要な場合もあります。
- 行政訴訟は代理人弁護士を依頼せずに独力で行うには荷が重い手続きです。経験と熱意のある弁護士に依頼することが必要です。
〔参考文献〕
9 補償交渉
過労死が発生した場合、遺族や被災者としては、企業の責任追及として、民事賠償、謝罪、再発防止措置などについて交渉することもできます。企業が、従業員が死亡した場合に独自の補償制度を持っている場合があります。このような補償制度を持っている場合、会社から制度に基づいた保証補償を受け取ることができます。
そのような独自の制度がをなくとも、会社は、労働者の業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷党が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(安全配慮義務)を負っていますので、会社がこのような義務に反しているとして、企業に損害賠償金を支払うように求めることも可能です。
このような義務違反は、長時間労働に従事させ業務軽減措置怠るなど、労働条件について十分に配慮していない場合や、健康診断を実施していないなど、十分な健康管理体制をとっていない場合などに認められます。
補償を求める内容は、逸失利益、慰謝料、葬祭業、弁護士費用、遅延損害金などです。逸失利益とは、過労死や過労自殺がなければえられた得られたであろう将来の収入等の利益を指します。慰謝料は、死亡に対する労働者自身の精神的損害と、遺族固有の精神的損害の両方を請求することができます。その他の損害としては、葬祭業・休業した場合の損害・治療費・付き添い看護費、後遺症が残った場合の将来の介護費用、家屋改装費なども損害として請求することができます。
なお、法律的な請求の根拠は、主に安全配慮義務違反と不法行為の2種類があり、最も大きな違いは、時効(前者が10年、後者が被害を知ってから3年)です。一方で、不法行為の方が、遅延損害金の発生が早まることや、弁護士費用の請求が認められやすい点も違いとして指摘できます。
会社に対しては、多くの場合、労災認定が下りてから交渉します。その方が企業に責任を認めさせやすいからです。しかし、事情によっては労災申請と並行してまたは労災申請より前に(労災申請をせずに)補償の交渉を行う場合もあります。現在の労災認定基準が不十分であるため、労災認定を得ることが困難な場合でも、会社に対する責任追及はあり得ます。
したがって、働き過ぎが原因でなくなったり健康を損ねたりした場合、弁護士などの専門家に相談して、労災申請や企業との交渉など、どのような手段はとれるか検討してみることをお勧めします。
また、交渉によることで、謝罪や、再発防止措置をとることの約束をとりつけることも可能で、過労死を防ぐためにも重要になります。
もし、企業が交渉に応じない場合、裁判所の手続き(訴訟、労働審判等)を用いることとなります。
10 損害賠償訴訟
過労死が発生した場合、多くの場合、労災申請をしたり、補償の交渉をしたりすることとなりますが、補償の交渉に相手が十分応じなかった場合には、会社に対して、損害賠償請求訴訟を起こすことになります。
その根拠は、9でも書いている通り、会社が労働者の業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷党が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反(安全配慮義務違反)したとする、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求です。
請求項目は、これも、9で書いた通り、逸失利益、慰謝料、葬祭業、弁護士費用、遅延損害金などです(内容の詳細は「9. 補償交渉」をお読み下さい)。
なお、債務不履行による時効は、損害が発生した時点から10年(2020年4月以後は5年)、不法行為の場合は、損害を知った時から3年です。
また、多くの場合、労災申請を先に行って、労災認定を得てから損害賠償請求を行います。労災認定を得れば、会社の損害賠償請求もしやすくなるからです。さらに、労災認定にあたって労働基準監督署が手に入れた資料も、個人情報開示手続きによって被災者側も手に入れて利用することも可能です。
損害賠償請求訴訟にあたっては、重い心臓病があって、それが影響して過労による心臓疾患になった場合等、当事者の公平を理由として、損害賠償請求額が減額されることもあります。
さらに、労災認定を得ている場合、すでに給付を受けた金額分の一部(逸失利益)と、葬祭料が控除される可能性があります。
最後に、元々うつ病など精神疾患を持っていた労働者が過労・ハラスメントなどによって症状を悪化させ、自死に至った場合等で、労災認定を得ることが難しいケースであっても、企業の自殺防止義務などを理由に損害賠償請求が認められたケースもあります。
どのような請求が可能になりうるのか等、専門家に相談することをお勧めいたします。
11 労働審判、民事調停
労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。通常の訴訟とは異なり、原則として申立てから40日以内に設定される第1回期日の中で、法的な結論が示されるという迅速な手続であることが大きな特徴です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行することになります。
過労死事件の場合には、勤務先に対する損害賠償を請求する場面で労働審判を活用することが考えられます。
紛争解決のための手段としては、他にも民事調停という手続があります。調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。
手続が簡単で、話し合いに基づく円満解決を目指すことができるという点が大きな特徴になります。他方で、訴訟とは異なり、相手方が話し合いに応じる姿勢がなければ不成立に終わってしまうため、相手方の姿勢次第では解決の実効性が薄いという点はデメリットと言わざるを得ません。
過労死事件の場合には、労働審判と同じく、勤務先に対する損害賠償を請求する場面で民事調停を活用することが考えられます。