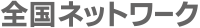意見書
- 脳・心臓疾患の労災認定基準の改定を求める意見書
- 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 2003年過労死弁護団全国連絡会議改定案
- 精神障害・自殺の労災認定に関する意見書
- 精神障害・自殺判断指針改定意見書
- [表] 精神障害・自殺労災判断指針改定案(2009年)
- 法定利率・中間利息控除に関する意見書
- 心理的負荷による精神障害の認定基準(発1226第1号 平成23年12月26日)「第5精神障害の悪化業務起因性」改定を求める意見書
脳・心臓疾患の労災認定基準の改定を求める意見書
厚生労働大臣 坂口 力 殿
代表幹事弁護士 岡村親宜
同 水野幹男
同 松丸 正
貴省は、2001年12月12日、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)の認定基準を改定した(基発第1063号。以下「認定基準」という。)。
認定基準は、過重負荷評価期間を原則6か月とし、過重負荷評価基準を緩和し、業務との関連性が強い時間外労働時間数を明示するなど、被災労働者及びその遺家族の補償を拡大するものであり、評価できる。
しかし、認定基準改定の契機となった、2000年7月17日の最高裁判決(※[最判1-(1)]及び[最判1-(2)]、別紙「2000年7月17日最高裁判決以後の主な労働者側勝訴判例の一覧」参照)は、1995年2月1日に改定された従前の脳・心臓疾患の認定基準(基発第38号。以下「旧認定基準」という。)を根本的かつ全面的に見直すべきことを提起したが、認定基準はこの最高裁判例の水準に達していない。また、脳・心臓疾患の発症後に業務のため治療機会を喪失した事案について認定基準は「業務上」と認定する途を閉ざしているが、認定基準改定前後に、最高裁判所は、このような事案についても「業務上」と認定する判決を言い渡し、このような事案をも「業務上」とするよう認定基準が改定されるよう提起したものである。
そして、2000年の最高裁判決後の下級審判例の水準、さらには専門検討会報告書に紹介された医学的知見に照らしても、認定基準には以下の4点の問題がある。
- 貴省の採用する相対的有力原因説は破綻している。
- 治療機会喪失事案の救済を拒否している。
- 過重負荷評価基準が厳格である。
- 業務との関連性が強いとされる時間外労働時間数の基準が高すぎる。
- 労働時間(労働の量)以外の労働の質の要因を限定的にしか考慮していない。
過労死弁護団全国連絡会議は、現在の判例水準等を踏まえ、以下のとおり、認定基準を改定するよう要求するものである。
※ 本意見書における判例の略称については、別紙「2000年7月17日最高裁判決以後の主な労働者側勝訴判例の一覧」の第1の最高裁判例の場合、例えば、横浜南労基署長(東京火災海上保険横浜支店)事件・最高裁一小平12.7.17判決は[最判1-(1)]、尼崎労基署長(森永製菓塚口工場)事件・最高裁三小平13.9.11決定は[最決2-(4)]と表す。第2の下級審判例の場合、例えば、脳心臓疾患事案の佐伯労基署長(伊賀荷役)事件・福岡高裁平12.9.27は[判例1-(1)-(1)]と表す。
第1 「基本的な考え方」の改定の必要性
〈改定意見の趣旨〉
貴省は、第1の「基本的考え方」を下記のとおり改定すべきである。
記
「業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものである。」
「また、既に何らかの原因で安静を必要とする脳・心臓疾患を発症又は増悪した後、引き続き業務に従事せざるを得ないような状況の下で業務に従事し、その結果、脳・心臓疾患を増悪させ又は増悪により死亡した場合があり、そのような経過をたどり増悪した脳・心臓疾患についても、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものである。」
〈改定意見の理由〉
認定基準は、第1の「基本的な考え方」において、「業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合」に、「業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱う」とし、1987年10月26日基発第620号の認定基準以来の相対的有力原因説を堅持し、「相対的に有力な原因」の内容を、業務が血管病変等の自然経過を超えて著しく増悪させて脳・心臓疾患が発症させた場合であると定義した。
旧認定基準が「業務が急激な血圧変動や血管収縮を引き起こし、血管病変等をその自然経過を超えて急激に著しく増悪させ発症に至った場合には、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することが明らかな疾病とする」としているのに対し、認定基準が「急激に」の文言を削除したことは評価できる。
しかし、近時、脳・心臓疾患発症のリスクファクターを有する高齢者の雇用拡大が期待されているが、業務による過重負荷が基礎疾患等を自然経過を超えて著しく増悪させなければ救済されないとすると、特に基礎疾患等を有する高齢者の救済が厳しく限定されるおそれがある。
[最判1-(1)]は、血管病変等の自然経過を超える増悪が「急激に」であることも「著しく」であることも必要であると判示しておらず、また、[最決(3)]は、[最判1-(1)]に従って労働者側を勝訴させた[判例1-(1)-(1)]を是認し、厚生労働省の上告受理申立てを受理しない旨の決定をした。さらに、[最判1-(1)]の後に言い渡された下級審判例のうち、[判例1-(1)-(2)]、[判例1-(1)-(4)]、[判例1-(1)-(6)]、[判例1-(1)-(8)]、[判例1-(1)-(9)]、[判例1-(1)-(12)]、[判例1-(1)-(16)]、[判例1-(1)-(17)]、[判例1-(2)-(2)]、[判例1-(2)-(3)]、[判例1-(2)-(4)]、[判例1-(2)-(5)]、[判例1-(2)-(7)]、[判例2-(2)]、[判例2-(4)]、[判例3-(1)]、[判例3-(2)]及び[判例3-(3)]が「急激に」も「著しく」も不要と判示しているものであり、下級審判例の多くが[最判1-(1)]に従った判断を示しているものである。
それにもかかわらず、医学専門家と法律専門家が参集して検討した結果をまとめた専門検討会報告書及び認定基準は、なぜ「著しく」の文言を残したのかについて医学的にも法理論的にも全く根拠を示していない。
また、貴省は、認定基準の制定により、「相対的に有力な原因」な業務の内容を変更しており、この変更の経過からすれば、「相対的に有力な原因」の内容自体、極めて曖昧かつ政策的な意味合いの強いものであるから、貴省が採用する「相対的有力原因説」は法理論的には全く破綻しているというべきである。
そこで、貴省は、「急激に」の文言だけでなく、「著しく」の文言も削除すべきである。
さらに、後記第2のとおり、治療機会喪失事案についても、「業務上」と認定するよう改定すべきである。
よって、貴省は、第1の「基本的考え方」を上記のとおり改定すべきである。
第2 認定要件の改定の必要性
〈改定意見の趣旨〉
貴省は、下記のとおり、治療機会喪失事案についても「業務上」と認定するよう、第3の認定要件に追加すべきである。
記
「脳・心臓疾患を発症又は増悪し、直ちに安静を保ち適切な治療等を受ける必要があったにもかかわらず、引き続き業務に従事せざるを得ない状況の下で業務に従事し、その結果、脳・心臓疾患を増悪させ又はその増悪により死亡したこと」
〈改定意見の理由〉
[最判2-(1)]は、労作型の不安定狭心症を発症した当日及び翌日に公務に従事した高校体育教諭が、入院の上適切な治療と安静を必要とし、不用意な運動負荷をかけると心筋梗塞に進行する危険の高い状況であったにもかかわらず、直ちに安静を保つことが困難で、引き続き公務に従事せざるを得ず、その結果心筋梗塞を発症して死亡した事案につき、同教諭の死亡は「公務上」の死亡に該当すると判断した。
[最判2-(1)]は、このような治療機会喪失事案についても「業務上」とすることを提起したにもかかわらず、報告書は、脳・心疾患の発症後に業務のため治療機会を喪失した事案の救済の必要性について全く検討しておらず、認定基準も、このような事案について「業務上」と認定する途を閉ざしたが、救済範囲を狭くするものであり、批判されるべきである。
ところで、貴省が2000年10月12日に脳・心臓疾患の認定基準の見直しを発表した前後に、中央労基署長(永井製本)事件・東京高裁2000年8月9日判決(労判797号)及び尼崎労基署長(森永製菓塚口工場)事件・大阪高裁2000年11月21日判決(労判800号)は、治療機会の喪失を理由に、被災労働者の死亡は「業務上」の死亡に該当すると判断した。
これに対し、貴省は、いずれの事件も上告受理申立てをして、上告受理申立理由につき、両事件で要件論の内容、位置づけについて食違いが見られるものの、要旨、
- 労働者の死亡等が「業務上」のものと認めるためには、条件関係だけでは足りず、相当因果関係が必要であり、
- 治療機会喪失事案においては、「労働者にとっては遂行中の業務を中断して職場を離れ得ない事情がある場合、あるいは自宅等での発症でも休暇を取得し得ず、出勤を余儀なくされる場合等引き続き業務に従事せざるを得ないような客観的状況に置かれる場合」に例外的に相当因果関係が認められるとし、
- その要件として、(1)安静治療の必要性、(2)治療機会の可能性、(3)労働者自身による体調不良の認識、(4)当該就業の不可避性が認められることが必要である、
とし、治療機会喪失事案の「業務上」認定の範囲は限定されるべきであると主張した。
しかしながら、[最決2-(4)]及び[最決2-(5)]は、それぞれ上記原審高裁判決を相当とし、貴省の上告受理申立てを受理しない旨の決定をし、貴省の治療機会喪失事案救済限定論を採用しなかったものである。
最高裁判例は、治療機会喪失事案について、従来の業務過重性判断とは別個の、業務と発症との相当因果関係を認める一類型を新たに認めたものであり、貴省が治療機会喪失事案について「業務上」と認定せずに救済を拒否していることは、最高裁判例に違反しているというべきである。
したがって、貴省は、治療機会喪失事案の救済拒否の政策を転換し、上記のとおり同事案についても「業務上」と認定するよう、第3の認定要件に追加すべきである。
そして、治療機会喪失事案の業務起因性は、(1)安静治療の必要性と、(2)発症後に業務に従事せざるを得なかったことを、疾病の性質や症状(自覚症状、他覚所見)の程度、進行状況、業務の内容及び性質、被災労働者の地位及び責任の内容、人員配置などの職場環境、発症後の業務の具体的遂行状況、発症後の使用者の対応状況等の事情を総合して、判断すべきである。
第3 過重負荷評価基準の改定の必要性
認定基準が、旧認定基準の「当該労働者と同程度の年齢、経験等を有し、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある者」に加えて「基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者」も過重負荷評価基準の対象として、基準を緩和したことは評価できる。
しかし、以下の問題点があり、認定基準第4の2の(2)のウの(ア)は改定されるべきである
1 当該被災労働者を基準とすることの相当性
〈改定意見の趣旨〉
貴省は、下記のとおり、業務による過重負荷を当該被災労働者を基準として評価するよう、認定基準第4の2の(2)のウの(ア)を改定すべきである。
記
「特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、当該労働者にとって、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かを判断する。」
〈改定意見の理由〉
[最判1-(1)]は、被災労働者と同程度の年齢、経験等を有し、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある同僚又は同種労働者にとっても特に過重な精神的・身体的負荷を生じさせたと認められるか否かを全く検討することなく、被災労働者の従事した業務が、同人にとって、過重な精神的・身体的負担を生じさせ得る質的に又は量的に過重な業務であり、同人の動脈瘤の血管病変を自然経過を超えて増悪させ、くも膜下出血発症に至る原因となったことを認め、当該被災労働者を過重負荷評価基準にするのが相当であると判示した。また、[最判1-(1)]の後に言い渡された下級審判例のうち、少なくとも、[判例1-(1)-(2)]、[判例1-(1)-(4)]、[判例1-(1)-(5)]、[判例1-(1)-(6)]、[判例1-(1)-(13)]、[判例1-(2)-(3)]、[判例1-(2)-(4)]、[判例1-(2)-(5)]及び[判例2-(1)]は、実質的には[最判1-(1)]に従って当該被災労働者を基準にして過重負荷を評価していると考えられる。この裁判例の動向は、脳・心臓疾患の発症には個体差を無視することはできず、また、平均的労働者基準説を形式的に貫徹すると日常業務が過重である場合には実質において不合理な結果をもたらすことによるものである。したがって、同種労働者を過重負荷評価基準とする認定基準は、最高裁判例及び多くの下級審判例に違反しているというべきである。
また、高齢者や身体に障害を有する者の雇用拡大が期待される近時の雇用状況に照らしても、あくまで同種労働者を過重負荷評価基準とするのでは救済範囲を狭くするものというべきである。
よって、貴省は、上記のとおり、業務による過重負荷を当該被災労働者を基準として評価するよう、認定基準第4の2の(2)のウの(ア)を改定すべきである。
2 同種労働者のうち最も弱い者を基準とすることの相当性
〈改定意見の趣旨〉
仮に当該被災労働者を過重負荷評価基準にするのが相当でないとしても、貴省は、下記のとおり、業務による過重負荷を同種労働者のうち脳・心臓疾患発症の危険に対する抵抗力が最も弱い者を基準とし、当該被災労働者の基礎疾患等が通常想定される範囲を外れるものでない限り、当該被災労働者を基準として評価するよう、認定基準第4の2の(2)のウの(ア)を改定すべきである。
記
「特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、当該労働者と同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で、業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中で脳・心臓疾患発症の危険に対する抵抗力が最も弱い者(ただし、同種労働者の基礎疾患等の多様さとして通常想定される範囲内の者)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かを判断するが、当該労働者の基礎疾患等が同種労働者の基礎疾患等の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、当該労働者にとって、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かを判断して差し支えない。」
〈改定意見の理由〉
[判例2-(2)]は、過重負荷評価基準を「同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で、業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし、同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者)をと」し、「同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準とするということは、被災労働者の性格傾向が同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、当該被災労働者を基準と」するのが相当とした(判決書104頁)。この控訴審判決である[判例2-(4)]は、[判例2-(2)]が判示した基準を是認した上で、この基準は精神障害等の労災認定に係る専門検討会報告書及び心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(1999年9月14日基発第544号)と共通していると判示し(判決書50頁)、貴省に対し、過重負荷評価基準を見直すよう提起したものである。
また、[判例1-(1)-(9)]及びこの控訴審判決である[判例1-(1)-(12)]は、基礎疾患等により日常業務を支障なく遂行することができなくても、通常の軽作業に従事することが可能な労働者を基準として、すなわち脳・心臓疾患発症の危険に対する抵抗力が最も弱い者を基準として、業務の過重性を判断すべきであると判断したものである。
したがって、貴省は、上記のとおり、業務による過重負荷を同種労働者のうち脳・心臓疾患発症の危険に対する抵抗力が最も弱い者を基準とし、当該被災労働者の基礎疾患等が通常想定される範囲を外れるものでない限り、当該被災労働者を基準として評価するよう、認定基準第4の2の(2)のウの(ア)を改定すべきである。
第4 過重負荷要因の改定の必要性
認定基準が、過重負荷要因として、
(1) 労働時間につき、発症日を基点とした1か月単位の連続した期間をみて、発症前1か月間ないし6か月間にわたって、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価でき、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できると明示したこと、
(2) 労働時間以外の要因として、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い勤務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境(温度環境、騒音、時差)、精神的緊張を伴う業務を明確化したこと、
は評価できる。
しかし、以下の問題点があり、認定基準第4の2の(2)のウの(ウ)及び第4の2の(2)のエの(イ)は改定されるべきである
1 発症との関連が強い時間外労働時間数(労働の量)の改定の必要性
〈改定意見の趣旨〉
貴省は、下記のとおり、認定基準第4の2の(2)のエの(イ)において定める、業務と発症との関連性が強いとされる時間外労働時間数を改定すべきである。
記
「発症日を基点とした1か月単位の連続した期間をみて、発症前1か月間ないし6か月間にわたって、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること、発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1週間当たり15時間、4週間当たり60時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」
〈改定意見の理由〉
認定基準の改定後、各地で行政処分取消訴訟係属中及び労働保険審査会再審査請求中の脳・心臓疾患の労災保険給付不支給処分事件について、労基署が自らの誤りを認めて支給処分を行った。この点は評価できるが、発症前1か月間に100時間以上又は6か月間に80時間以上の時間外労働をしていたことが認められる事例が多い。
しかしながら、1か月当たり45~80時間の時間外労働をしている労働者は相当数おり、この程度でも過労死しているのが現実であり、特に交替制勤務や不規則勤務に従事している労働者は、1か月当たりの時間外労働が45時間以下でも過労死しているのが現実である。認定基準が定める時間外労働時間数を形式的に適用するならば、高いハードルを設定して、かえって認定基準が業務外とする基準となる危険が高く、多数の脳・心臓疾患を発症した労働者の救済が閉ざされる危険性が高い。
実際に、現場の実務では、業務との関連性が強いとされる時間外労働時間数を超えていれば比較的早期に業務上の認定がなされるようになったが、認定基準が業務との関連性が強いとする、発症直前1か月当たりおおむね100時間を超える時間外労働、又は発症前2か月ないし6か月にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働をしていなければ、杓子定規に適用されて、業務外の認定をされて救済が拒否されている例が多い。
これに対し、近時の下級審判例([判例1-(1)-(10)]、[判例1-(1)-(11)]、[判例1-(1)-(13)]、[判例1-(1)-(16)]、[判例1-(1)-(17)]、[判例1-(2)-(4)]、[判例1-(2)-(6)]及び[判例1-(2)-(7)])は、必ずしも認定基準が業務との関連性が強いとする時間外労働時間数に達していなくても、不規則勤務、交替制・深夜勤務、出張業務、精神的緊張を伴う業務の性質・内容等の労働の質の過重性を重視して、「業務上」の認定をしているところである。
それでは、認定基準が業務との関連性が強いとする時間外労働時間数は合理的な根拠があるといえるのか。
認定基準が定めた時間外労働時間数の根拠は、旧総務庁「平成8年社会生活基本調査報告」及び(財)日本放送協会「2000年国民生活時間調査報告書」を基に、労働者の1日の平均的な生活時間として「仕事(拘束時間)」の時間9時間、「睡眠」の時間7.4時間、「食事等」の時間5.3時間、「余暇」の時間2.3時間とした(98頁)上で、「1日6時間程度の睡眠が確保できない状態は」、「1日の労働時間が8時間を超え、4時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね80時間を超える時間外労働が想定される」、また、「1日5時間程度の睡眠が確保できない状態は」、「1日の労働時間8時間を超え、5時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね100時間を超える時間外労働が想定される」(96頁)とし、「1日7.5時間程度の睡眠が確保できる状態」は、「1日の労働時間8時間を超え、2時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これは、1か月おおむね45時間の時間外労働が想定される」(97頁)と報告していることにある。
しかし、報告書は、「仕事(拘束時間)」の時間を、1日の法定労働時間8時間と休憩時間1時間を足した9時間とし、これを大前提として、「睡眠」、「食事等」、「余暇」の各時間を算定しているが、その根拠を何ら示しておらず、専門検討会において検討した様子は全く見受けられない。このように生活時間の算定根拠が曖昧であり、また、特に首都圏の労働者が往復の通勤に3~4時間をかけている例が珍しくないのが実態であることからすると、各時間数の算定には疑義がある。
また、労働者の1日の平均的な生活時間である「余暇」の時間2.3時間のうち0.1時間を「睡眠」の時間に充てて7.5時間の睡眠時間を確保し、人間の生理的に必要な時間と通勤時間を足した時間である「食事等」の時間を5.3時間のままとすると、残りの「余暇」の時間2.2時間を時間外労働に充てることができるが、そうすると、「余暇」の時間が全くなくなってしまい、総務庁及び日本放送協会の調査においても現代の日本人が特に新聞・ラジオ・テレビに多くの時間を割いている傾向にあることが報告されていることと合致しない。
そして、1日の「睡眠」の時間が6時間又は5時間である場合、「余暇」の時間を0時間にし、「食事等」の時間を5.3時間のままとすると、1日の時間外労働時間は3.7時間又は4.7時間となり、月換算ではおおむね80時間又は100時間となるが、現実の通勤時間や余暇時間を考えると、やはり報告書の算定は実態に合致していないというべきである。
1日8時間労働の原則を定め、労働者の人たるに値する生活を保障した労働基準法の趣旨、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とした労災保険法の趣旨からすれば、1日の「余暇」の時間が0時間で、労働者が生活するのに必要な「食事等」の時間も削らなければならないほどの時間数の時間外労働に従事しなければ、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価せずに補償を拒否するのは、高いハードルを設定して、かえって業務外の判断をする危険性が高く、何ら合理的な根拠はないというべきである。
しかも、報告書は、1日3時間程度、月60時間程度の時間外労働は脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとの医学研究報告を紹介しているが(92~94頁)、これらの報告によれば、報告書と認定基準のいう脳・心臓疾患の発症との関連が強い時間外労働時間数は、医学的な研究結果と合致せず、医学的な根拠を有しないといわざるを得ない。
そして、いわゆる36協定の労働時間の延長の限度等に関する基準を定めた1998年12月28日労働省告示154号が1週間の延長時間の限度を15時間と定めていることに鑑みれば、発症前1か月ないし6か月間にわたって、1週間あたり15時間、4週間あたり60時間を超える時間外労働が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと判断すべきである。
したがって、貴省は、上記のとおり、業務と発症との関連性が強いとされる時間外労働時間数を改定すべきである。
2 労働時間以外の要因(労働の質)の改定の必要性
ア 不規則な勤務について
認定基準における「不規則な勤務」は、予定された業務のスケジュールや内容の変更を意味し、早出や遅出がある勤務形態を含まず、範囲が限定されている。
しかし、[最判1-(1)]は、不規則勤務の過重性を判断するにあたって、このような限定をしておらず、[判例1-(1)-(13)]も不規則勤務自体の過重性を認めていることからすれば、この認定基準は判例に違反しているというべきである。
したがって、貴省は、不規則な勤務があればこれ自体を過重負荷の要因とするよう認定基準を改定すべきである。
また、人事院の「心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について」と題する通知(2001年12月12日勤補-323)が「早出、遅出等不規則勤務」を過重負荷の評価事情に挙げていることからすれば、認定基準も「不規則な勤務」に早出、遅出等の勤務を追加すべきである。
イ 交替制勤務、深夜勤務について
認定基準は過重負荷の評価事情として「交替制勤務、深夜勤務」を挙げているが、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準の運用上の留意点等について」と題する事務連絡(2001年12月12日基労補第31号)は、「交替制勤務が日常業務としてスケジュールどおり実施されている場合や日常業務が深夜時間帯である場合に受ける負荷は、日常生活で受ける負荷の範囲内と評価される」としており、勤務シフトの変更等がある場合に限定している。
しかし、報告書では紹介されていないが、1998年度労働省委託研究報告書「深夜業の健康影響に関する調査研究」(1999年2月、産業医科大学)によれば、深夜勤務自体が血圧等身体に影響を及ぼす可能性が指摘されていること、また、人事院の認定指針が何らの限定をせずに過重負荷の評価事情として「深夜勤務、交替制勤務、宿直勤務」を挙げていること、さらに、[判例1-(2)-(4)]、[判例1-(2)-(6)]及び[判例1-(2)-(7)]が交替制・深夜勤務自体の過重性を認めていることからすれば、長期間にわたる交替制勤務や深夜勤務に従事していた場合にはそれ自体をもって過重負荷と評価するよう改定すべきである。
そして、第6回専門検討会において配布されたドラフトには、「日本産業衛生学会交代勤務委員会の意見書やILO、NIOSH等の健康影響の予防としての勧告を参照したおおよその予防的な労働態様である、(1)深夜業を含む勤務回数が1ヶ月に10回以下であること、(2)深夜勤務が連続して5夜以上続かないこと、(3)深夜勤務前あるいは深夜勤務後のシフトとの間隔が8時間未満であるような勤務が週2回以下であることなどを参考にして、業務がこれらの勧告よりも著しく過重であり、業務による疲労の発生とその蓄積をもたらさない休息や睡眠をとる時間的余裕がなかったかが過重性の評価の目安となる」と記載されているが、報告書では何故か脱落している。業務の過重性を判断するに当たっては、これらの勧告を無視する理由はなく、逆にこれを重視すべきであり、勧告を超える回数の深夜勤務をし、その回数が多くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価すべきである。
ウ 作業環境について
認定基準は、作業環境については、「脳・心臓疾患の発症との関連性が必ずしも強くない」ことを根拠に、過重性の評価に当たっては付加的にしか考慮しないとしている。これに対し、人事院の認定指針が「通常の日常の業務に比較して特に質的に若しくは量的に過重な業務」として「暴風雨、寒冷、暑熱等の特別な業務環境の下での業務を長時間にわたって行っていた場合」を挙げ、また、地方公務員災害補償基金の「心・血管疾患及び脳血管疾患等の職務関連疾患の公務上災害の認定について」と題する通知(2001年12月12日付け地基第239号)が時間外勤務の評価とともに評価する職務従事状況等の要因として「著しい騒音、寒暖差、頻回出張等不快、不健康な勤務環境下における職務従事状況」を挙げており、いずれも「付加的」に評価するとの限定をつけていないことからすれば、認定基準においても、作業環境を「付加的」にではなく、他の要因と並列的に過重負荷の評価をするよう改定すべきである。
作業環境のうち、温度環境について、認定基準は、「なお、温度環境のうち高温環境については、脳・心臓疾患の発症との関連性が明らかでないとされていることから、一般的に発症への影響は考え難いが、著しい高温環境下で業務に就労している状況が認められる場合には、過重性の評価に当たって配慮すること」としているが、第6回専門検討会において配布されたドラフトには、「高温環境では循環器系への負担が大きいが、脳・心臓疾患の罹患率や死亡率を高めるとの調査結果はあまり得られていない」と記載されており、「高温環境については、脳・心臓疾患の発症との関連性が明らかでない」との認定基準の記載は意図的に高温環境下での作業の負荷を過小評価したものというべきである。したがって、上記のなお書きは削除すべきである。
また、第6回専門検討会において配布されたドラフトには、「冬季における屋外作業(農林水産業、土木・建設作業、保線・港湾作業、陸海上運輸業、除雪作業など)、多量の液体空気やドライアイスなどを取り扱う業務、冷蔵庫・製氷庫・貯氷庫・冷凍庫などの内部で行う作業、あるいは生鮮食料品の加工・包装・流通職場などが、脳・心臓疾患を引き起こす可能性がある業務に該当する」と記載されているが、専門検討会報告書では何故か脱落している。専門検討会報告書が上記の記載を何らの理由もなく脱落させた合理性はなく、上記のドラフトのとおり、これらの業務に従事していた場合にはそれ自体をもって過重負荷と評価するよう改定すべきである。
エ 精神的緊張を伴う業務について
認定基準は、精神的緊張を伴う業務として、労働災害や重大な事故・災害の遭遇、仕事上の大きなミス、ノルマの不達成、異動、業務上のトラブルを発症に近接した時期に限定している。
しかし、精神障害等の判断指針は、上記のライフイベントが精神疾患発症前6か月間に発生した場合は心理的負荷があることを認めている。これに対し、第10回専門検討会の議事録によれば、上記の出来事を、「日常的に精神的緊張を伴う業務上の出来事」とは別に、「発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事」に分けた理由として、座長は「分かりやすくする」としか説明しておらず、結局区別することには何らの合理的な理由はないのである。
したがって、認定基準も「精神的緊張を伴う業務」を「日常的に精神的緊張を伴う業務」と「発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事」を区分せず、後者の出来事が発症前6か月間に発生した場合でも「精神的緊張を伴う業務」と評価するよう改定すべきである。
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 2003年過労死弁護団全国連絡会議改定案
第1 基本的な考え方
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものとされている。
しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものである。
このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとした。
また、業務の過重性の評価に当たっては、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等を具体的かつ客観的に把握、検討し、総合的に判断する必要がある。
さらに、既に何らかの原因で安静を必要とする脳・心臓疾患を発症又は増悪した後、引き続き業務に従事せざるを得ないような状況の下で業務に従事し、その結果、脳・心臓疾患を増悪させ又は増悪により死亡した場合(以下「治療機会喪失事案」という。)があり、そのような経過をたどり増悪した脳・心臓疾患についても、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものである。
※強調部分は改定案。以下同じ。
第2 対象疾病
本認定基準は、次に例示する脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。
1 脳血管疾患
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞(脳血栓症、脳梗塞症、ラクナ梗塞)
- 高血圧性脳症
2 虚血性心疾患等
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む。)
- 重症の不整脈(心室細動等)
- 肺塞栓症
- 大動脈瘤破裂(解離を含む。)
第3 認定要件
次の(1)又は(2)の要件を満たす脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱う。
(1) 次のア、イ又はウの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患
ア 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
イ 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。
ウ 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 脳・心臓疾患を発症又は増悪し、直ちに安静を保ち適切な治療等を受ける必要があったにもかかわらず、引き続き業務に従事せざるを得ない状況の下で業務に従事し、その結果、脳・心臓疾患を増悪させ又はその増悪により死亡したこと。
第4 認定要件の運用
1 脳・心臓疾患の疾患名及び発症時期の特定について
(略)
2 過重負荷について
過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて増悪させ得ることが認められる負荷をいい、業務による明らかな過重負荷と認められるものとして、「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としたものである。
ここでいう自然経過とは、加齢、一般生活等において生体が受ける通常の要因による血管病変等の形成、進行及び増悪の経過をいう。
(1) 異常な出来事について
ア 異常な出来事
異常な出来事とは、具体的には次に掲げる出来事である。
(ア) 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態
(イ) 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態
(ウ) 急激で著しい作業環境の変化
イ 評価期間
異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。
ウ 過重負荷の有無の判断
異常な出来事と認められるか否かについては、
Ⅰ.通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったか、
Ⅱ.気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったか
等について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。
(2) 短期間の過重業務について
ア 特に過重な業務
特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。
ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。
イ 評価期間
発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
ウ 過重負荷の有無の判断
(ア) 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、当該労働者にとって、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かを判断すること。
(イ) 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、医学的には、発症に近いほど影響が強く、発症から遡るほど関連性は希薄となるとされているので、次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断すること。
(1) 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
(2) 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
なお、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合の継続とは、この期間中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に就労した日が間断なく続いている場合のみをいうものではない。したがって、発症前おおむね1週間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに業務起因性を否定するものではない。
(ウ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。
a 労働時間
労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については、十分に考慮すること。
例えば、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか、発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められるか、休日が確保されていたか等の観点から検討し、評価すること。
b 不規則な勤務
早出、遅出等を伴う不規則な勤務は、それ自体で質的な過重性が認められること。予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等の事情があれば、業務の質的な過重性をさらに付加するものと評価すること。
c 拘束時間の長い勤務
拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価すること。
d 出張の多い業務
出張については、出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等の観点から検討し、評価すること。
e 交替制勤務・深夜勤務
交替制勤務・深夜勤務は、それ自体で質的な過重性が認められること。勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交替制勤務における深夜時間帯の頻度等の事情があれば、業務の質的な過重性をさらに付加するものと評価すること。
(1)深夜業を含む勤務回数が1ヶ月に10回以下であること、(2)深夜勤務が連続して5夜以上続かないこと、(3)深夜勤務前あるいは深夜勤務後のシフトとの間隔が8時間未満であるような勤務が週2回以下であることを超える回数の交替制・深夜勤務をし、その回数が多くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること。
f 作業環境
※本文削除
(a) 温度環境
温度環境については、寒冷の程度、防寒衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖の状況、暑熱と寒冷との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度等の観点から検討し、評価すること。
※なお書き削除
冬季における屋外作業(農林水産業、土木・建設作業、保線・港湾作業、陸海上運輸業、除雪作業など)、多量の液体空気やドライアイスなどを取り扱う業務、冷蔵庫・製氷庫・貯氷庫・冷凍庫などの内部で行う作業、あるいは生鮮食料品の加工・包装・流通職場などの作業は、それ自体で質的な過重性が認められること。
(b) 騒音
騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。
(c) 時差
飛行による時差については、5時間を超える時差の程度、時差を伴う移動の頻度等の観点から検討し、評価すること。
g 精神的緊張を伴う業務
精神的緊張を伴う業務については、別紙の「精神的緊張を伴う業務」に掲げられている具体的業務又は出来事に該当するものがある場合には、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。
※別紙の「精神的緊張を伴う業務」の「日常的に精神的緊張を伴う業務」と「発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事」を区分を廃止する。
また、精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性については、医学的に十分な解明がなされていないこと、精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価すること。
(3) 長期間の過重業務について
ア 疲労の蓄積の考え方
恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。
このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断することとする。
イ 特に過重な業務
特に過重な業務の考え方は、前記(2)のアの「特に過重な業務」の場合と同様である。
ウ 評価期間
発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。
発症前おおむね6か月より前の業務についても、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価すること。
エ 過重負荷の有無の判断
(ア) 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、総合的に判断すること。
(イ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、労働時間のほか前記(2)のウの(ウ)のbからgまでに示した負荷要因について十分検討すること。
その際、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1週間当たり15時間、4週間当たり60時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
を踏まえて判断すること。
ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。
また、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強めるものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示すものである。
3 治療機会喪失事案について
治療機会喪失事案において、脳・心臓疾患の発症後に業務に従事したことにより、脳・心臓疾患が増悪し、又は増悪して死亡したと認められるか否かは、(1)安静治療の必要性と、(2)発症後に業務に従事せざるを得なかったことを、疾病の性質や症状(自覚症状、他覚所見)の程度、進行状況、業務の内容及び性質、被災労働者の地位及び責任の内容、人員配置などの職場環境、発症後の業務の具体的遂行状況、発症後の使用者の対応状況等の事情を総合して判断すること。
第5 その他
(略)
精神障害・自殺の労災認定に関する意見書
厚生労働大臣
人事院総裁
地方公務員災害補償基金理事長 御中
私たちは、1988年以来社会問題となっている「過労死」問題の解決のため、全国的に過労死弁護団を組織し、労災申請事件、不支給処分取消請求不服申立事件、不支給処分取消請求行政裁判事件、法定外補償請求事件、損害賠償事件等の事件を担当してきました。
ところで、警察庁の統計によれば、2003年の年間自殺者数は3 万4427人であり、6 年連続3万人を突破する極めて深刻な事態が続き、これらの自殺の相当数が業務による過労・ストレスが原因となったと推定され、関係者がこれらの自殺のないよう一層努力することが強く求められています。と同時に、現に発生した精神障害・自殺については、労災補償制度の制度目的に基づき適切な補償が実施されることが強く求められます。
この精神障害・自殺の労災補償につき、1999年に従前の原則業務外とする取扱いが転換され、相当数の事案が労災認定されるようになりましたが、以後5 年の運用の中で多くの問題点が明らかとなっており、厚生労働省は近い将来通達の改正を予定して検討を開始していると報じられています。
私たちは、さる10月1 、2 日に開催した第17回全国総会でこの精神障害・自殺の労災認定問題に関し討議しました。そしてこの度、その認定のあり方につき別記のとおり意見を集約し、ここに提出致します。
貴方におかれては、この意見を考慮され、速やかに精神障害・自殺の現行認定指針を抜本的に改正し、認定行政を改善されるよう要望する次第です。
なお、指針の改定にあたっては、被災者・遺族、当弁護団、その他労災実務の現状に熟知した者から広く意見を聴取し、民主的に選定された医学専門家だけでなく法律専門家を加えた公正な総合的専門家会議を設置し、公開による検討を行うよう強く要請する次第です。
| 〒113-0033 | 東京都文京区本郷2-27-17 過労死弁護団全国連絡会議 |
|
| 代表幹事 岡村親宜 同 水野幹男 同 松丸 正 |
||
記
第1 精神障害発病の原因として、ある出来事(ライフイべント)が起きたことが明確に認識される事実による「急性ストレス」のみならず、長時間労働、長期間にわたる多忙、単調な孤独な繰り返し作業、単身赴任、交替制勤務等の日常の労働生活により持続的に継続される状況による「慢性ストレス」が存在することを認め、業務による「慢性ストレス」が認められる場合にも「業務上」と認定するよう要件を変更する認定指針の改正を行うこと
現行認定指針制定の際に設置された労働省の専門検討会は、「検討概要」において、職場におけるストレス要因として、「ある出来事が起きたことが明確に認識される事実に係る」「急性ストレス」のほかに、「長く続く多忙、単調な孤独な繰り返し作業、単身赴任、交替勤務などのように持続的であり、継続される状況から生じる」「慢性ストレス」が存在していることを認め、業務による出来事(ライフイべント)による「急性ストレス」の他に「慢性ストレス」が精神障害発病の原因(環境からくるストレス)となることを認めながら、「検討結果」においては、精神障害の発病要因としては、出来事(ライフイベント)によるストレスだけを取り上げ、「慢性ストレス」を取り上げなかった。
しかし、精神医学においては、今日、精神障害の発病要因である「環境からくるストレス」には、労働者がその人生でたまにしか遭遇しない事件的出来事(ライフイベント)による急性ストレス(心理的負荷)よりも、むしろ長期間の日常生活において生ずる混乱や落ち込みのディリー・ハッスルズ(日常的煩わしさ)と言われている慢性ストレスが発病の原因として作用しているとされており、労働者が日常の労働生活により負担する「慢性ストレス」を発病要因と認めない認定要件を定める現行認定指針は根本的に改定する必要がある。
そして、その改定にあたっては、一般経験則に照らして、精神障害の発病の要因となり得る過重な慢性ストレス及び急性ストレスを「過重ストレス」とし、被災者がこの過重ストレスを生じさせたと認められる業務に従事したことと、被災者が業務による発病要因となり得る過重ストレスがなくても、業務以外のストレス及び個体側要因により発病したとは認められないこと、並びに被災者に他に精神障害を発病させる確たる要因が認められないこと、を要件とする認定要件に改定する必要がある。
名古屋高判03.7.8(トヨタ自動車事件)は、自動車会社の設計業務に従事していた係長が恒常的な時間外労働や残業規制により相当程度の心理的負荷を受けて精神的・肉体的に疲労を蓄積していたところ、2車種の出図期限が重なり出図が遅れによる強い心理的負荷を受け、かつ職場委員長への就任が決まり出図期限が遵守できなくなるのではないかとの不安・焦燥による心理的負荷が認められれば、これらを総合して「過重な慢性ストレス」が認められると認定し、指針の定める労働者がその労働生活においてたまにしか遭遇しない[別表1]の事件的出来事による「強」と評価される急性ストレスが存在せず、発病の原因は本人の個体側要因の脆弱性にあるとする行政機関の認定を否定している。
なお、精神障害の発病要因となる「慢性ストレス」を含む「過重ストレス」は、発病前6か月の間を対象とするのは相当でなく、おおむね1年間を対象とするのが相当というべきである。
第2 精神障害の発病の原因となる業務による「過重ストレス」の強度の評価の基準を、被災労働者とその遺家族の人間に値する生活を営むための必要を充たす最低限度の法定補償を迅速公平に行うという労災補償制度の制度目的に照らし、現行認定指針の定める多くの人々がどう受けとめたかという基準(健康な平均人基準)ではなく、当該労働者が置かれた立場や状況を充分斟酌して適正に心理的負荷の強度を評価する必要があり、同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準として評価するよう指針を改定すること
現行認定指針は、検討会報告書の検討結果が、精神障害の発病原因である「ストレスの強度は、環境からくるストレスを、多くの人々が、一般的にどう受け止めるかという客観的な評価に基づくものによって理解される」としていることを根拠に、「労働者災害補償制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因となった出来事をどのように受け止めたかではなく、多くの人々がどう受けとめたかという客観的な基準によって評価する必要がある」とし、認定要件として「発病前6か月の間に客観的に当該精神障害を発病するおそれのある業務による強い心理的負荷がみとめられること」が必要であるとしている。
しかし、補償対象は、業務と相当因果関係ある死傷病と解するのが相当であるとしても、前記労災補償制度の制度目的にてらせば、精神障害の業務上外の判断における業務によるストレスの強度の評価は、被災労働者本人が感じたままと理解するのは相当でないとしても、平均人基準ではなく、前記名古屋高判03.7.8(トヨタ自動車事件)が判示するとおり、「ストレスの性質上、本人の置かれた立場や状況を充分斟酌して」「ストレスの強度を客観的見地から評価することが必要」であり、「同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で、業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし、同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者)を基準」とするのが相当であり、指針は「当該労働者が置かれた立場や状況を充分斟酌して適正に心理的負荷の強度を評価するに足りるだけの明確な基準になっているとするには、いまだ充分とはいえず、うつ病の業務起因性を」指針の「基準のみをもって判断する」のは不相当というべきである。
そして同事件の名古屋地判01・2・23 が判示するとおり、「業務上の心身的負荷の強度は、同種の労働者を基準にして客観的に判断する必要がある」が、「被災労働者の性格傾向が同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、当該被災労働者を基準として」判断するのが相当というべきである。
また、大阪高判03.12.11(長田消防署事件)が判示しているとおり、経理・庶務等の事務に携わったことのなかった係長が、経理・庶務等の事務に携わり、過去に軋轢のあった上司が署長である消防署の管理係長に配置転換され、その配転が初めて携わる経理・庶務等の事務に対する不安及び緊張にとどまらず、その署長の下での人間関係に対する極度の不安及び緊張の緊張の加わったものであり、配転後にその署長から経理事務の決済の際に詳細なチェックをされ、疑問点毎に詳しい説明を求められ、前署長時代の会計帳簿上の使途不明箇所につき追及され、同署長が部下の管理係員の面前で大声で怒鳴り、書類を机にたたきつけたりした事等の事実による心理的負荷が認められれば、配転という出来事と上司とのトラブルという二つの出来事による心理的負荷として切り離して個々に評価するのではなく、これらを総合して発病要因と評価するのが相当というべきである。
かつて行政機関は、過労性脳・心臓疾患の業務上外認定につき、業務の過重性の判断基準につき、指針と同一の健康な同僚基準説を採用していたが(1987年10月26日付基発 620号)、その後これが不相当であることを認めて「当該労働者と同程度の年齢経験等を有し日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある者」を基準とするとし(1995年2 月1 日基発38号)、さらにこれが不相当であることを認めて「当該労働者と同程度の年齢経験等を有し、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある者」を基準とすると変更した(2001年12月12日基発1063号)。
したがってこの過労性脳・心臓疾患の基準に照らしても、精神障害の認定の場合には、職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準とするのが相当というべきである。
第3 社会通念(一般経験則)に照らし、(1)被災者が発病前おおむね1年間に精神障害の発病要因となり得る過重ストレス(慢性ストレス及び急性ストレス)の認められる業務に従事していたかどうか、(2)被災者の精神障害が業務以外のストレス及び個体側要因により発病したとは認められないかどうか、(3)被災者には他に精神障害を発病させる確たる要因は認められないかどうかを総合し、業務による心理的負荷が発病・増悪に一定程度以上の危険性を有していたと認められれば、業務起因性があると判断するよう認定指針を改定すること
現行認定指針は、認定要件として「発病前おおむね6か月の間に客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷」を必要とするとし、業務による職場における出来事が、心理的負荷の強度を修正する視点の評価で強度(III)と評価され、かつ出来事に伴う変化等を検討する視点による評価が「同種の労働者と比較して業務内容が困難で、業務量も過大である等」が認められ「相当程度過重」と評価される場合、及び、前記視点の評価で中度(II)と評価され、かつ「同種労働者と比較して業務内容が困難で恒常的な長時間労働が認められるか、過大な責任の発生・支援・強力の欠如等特に困難な状況」か認められ、「特に過重」と評価される場合のいずれかに該当しなければ、前記認定要件は充されないとしている。これは、(1)業務による心理的負荷、(2)業務以外の心理的負荷及び (3)個体側要因が競合(共働)して精神障害が発病する事実を認めた上で、精神障害は、今日では、単一の病因ではなく、素因、環境因(身体因、心因)の複数の病因が関与しているとされ、環境からくるストレスと個体側の反応性、脆弱性の相関関係で精神破綻が生じて発病し、この三つの要因を切り離してそのいずれが有力かを判断することは不可能であるにもかかわらず、これらの三つの要因を切り離して業務による心理的負荷が他の二つの要因と比較して相対的に有力と認められなければ業務起因性は認められないとする相対的有力原因説を採用したものである。
しかし、前記名古屋高判03.7.8(トヨタ自動車事件)が判示するとおり、前記精神障害の三つの発病原因を総合し、社会通念(一般経験則)上、被災者が従事していた業務によるストレスが「一定程度以上の危険性を内在または随伴していること」が認められれば業務起因性は肯定されるべきである。
従って、社会通念(一般経験則)に照らし(1)おおむね発病前1年間に精神障害の発病要因となり得る「過重ストレス」の認められる業務に従事していたかどうか、(2)被災者の精神障害が業務以外のストレス及び個体側要因により発病したとは認められないかどうか、(3)被災者には他に精神障害を発病させる確たる要因は認められないかどうかを総合し、業務による心理的負荷が発病・増悪に一定程度以上の危険性を有していたと認められれば、業務起因性があるとするよう認定指針を改定する必要がある。
第4 被災労働者が精神障害発病後、業務が原因となって精神障害を増悪させ、その結果自殺した場合につき、業務起因性があると判断するよう認定指針を改定すること
現行認定指針は、発病前の業務による心理的負荷と当該精神障害発病との相当因果関係が認められない限り、発病後の業務による心理的負荷と精神障害の増悪・自殺との相当因果関係が認められても「業務上」と判断することを閉ざし、これらを「業務上」と取扱わないこととしている。
しかし、労災認定で問題となる精神障害・自殺事件の多くは、被災労働者が精神障害を発病し、適切な精神科の診療を受ける必要があったにもかかわらずこれを受けず、発病後も引き続き業務に従事して精神障害を増悪させ、ついには自殺に至っているのである。典型的な精神障害であるICD10の「うつ病エピソード」は、症状の程度により、(1)軽症、(2)中等症、(3)重症に分類され、軽症は通常症状に悩まされて日常の仕事や社会的活動を続けるのにいくぶん困難を感じるが完全に機能できなくなることはない、中等症は通常社会的、職業的あるいは家庭的な活動を続けていくのがかなり困難になる、重症はごく限られた範囲のものを除いて社会的、職業的あるいは家庭的な活動はほとんどできないとされている。
したがって、被災者が業務に起因しない軽症うつ病エピソードを発病し、適切な精神科の診療を受けさせる必要があったにもかかわらず事業者がこれを受けさせず、発病後も引続きこれを増悪させる業務に従事させて中等症もしくは重症に増悪させ、自殺するに至らせた場合には、発病後の業務による心理的負荷とうつ病の増悪もしくは自殺との相当因果関係は認められ、「業務上」と取扱うのが相当というべきである。
第5 労災保険法12条の2 の2 第1 項の「故意」とは、「結果の発生を意図した意思」ではなく、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けようとする意思」と解し、精神障害を発病した者の自殺はこの意味での「故意」は存在しないと推定され、その自殺は自殺念慮の症状が原因と推定されるから業務起因性があると判断するよう認定指針を改定すること
現行認定指針は、労災保険法第12条の2 の2 第1 項の「故意」につき、故意因果関係中断説を維持し、「故意」とは、「自分の一定の行為により負傷又はその直接の原因となった事故を意図した場合」をいうとの解釈(1965・7・31付基発 901号)を維持し、「結果の発生を意図した意思」と解し、「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺したと認められる場合には、結果の発生を意図した『故意』には該当しない」とし、精神障害に罹患している者の自殺についてのみその取扱いを変更し、精神障害に罹患していない者の自殺については従前どおり「故意」があるとし、「業務上」と取扱わないとの解釈を維持している。
しかし、人間の意思決定は、現実にはその者のおかれている諸条件に制約されており、因果関係の展開における一契機にすぎず、因果関係の中断は存在せず、故意因果関係中断説は観念論であり、意思決定が存するだけで因果関係の中断を認めるとのわが国の行政機関の解釈は、現実に業務上の事故や負担が自殺の動機になることがしばしばあることから見て、事実に適合しないだけでなく、法的因果関係論における法的論理として不相当というべきである。自殺は、結果の発生を意図した「故意」があっても、そして被災者が業務と相当因果関係のある精神障害に罹患していなくても、自殺の動機と被災者の自殺前に従事していた業務との相当因果関係が認められれば業務起因性を肯定するのが相当というべきである。労基法78条の趣旨は、休業補償及び障害補償を詐取しようとして手指を切断する等の自傷行為又は自損行為による負傷にはその補償を行わないことができることを明らかにした休業補償及び障害補償の補償制限規定であり、労災保険法12条の2 の2 第1 項の趣旨も、この労基法78条の趣旨と対応したものと解するのが相当というべきであり、自殺した労働者が結果の発生を企図する「故意」を有していたとしても業務との相当因果関係が認められる事故については、同項の適用がないと解するのが相当というべきである。
したがって、労災保険法12条の2 の2 第1 項の「故意」とは、「結果の発生を意図した意思」ではなく、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けようとする意思」と解するのが相当であり、精神障害を発病した者の自殺はこの意味での「故意」は存在しないと推定され、その自殺は自殺念慮の症状が原因と推定されるから業務起因性があると判断するよう認定指針を改定する必要がある。
精神障害・自殺判断指針改定意見書
厚生労働大臣 長妻 昭 殿
私たちは、1988年以来、社会問題となっている「過労死」問題の社会的救済のため、全国的に過労死弁護団を組織して取り組んできました。しかし、近年、過重な心理的負荷のある労働により、精神障害を発症し、そればかりか自殺して死亡し、被災者と遺家族の生活が破壊される深刻な事態(以下「過労自殺問題」という)が続いているにもかかわらず、労災補償による社会的救済の道は狭く、私たちは大きな困難に直面してきました。
1999年9月14日に制定された「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)は、それ以前の原則業務外との取扱いが転換され、相当数の事案が労災認定されるようになりましたが、その後、多くの問題点が明らかとなっています。私たちは、御庁宛、2004年11月22日付で「精神障害・自殺の労災認定に関する意見書」を提出し、現行判断指針の問題点を全面的に検討し、判断指針を改定するよう意見書を提出しました。しかし、御庁は、私たちのこの意見書を無視し、今日まで、現行判断指針の見直しを一切行わず、判断指針を改定しませんでした。
ところで、御庁は、昨年12月10日、現行判断指針の別表1の職場心理負荷評価表の「業務上の具体的出来事等に関する検証・検討を行う」との趣旨・目的で、「職場における心理的負荷評価表の見直し等に関する検討会」(以下「見直し検討会」という)を設置しました。見直し検討会は、昨年12月25日に第1回検討会を、本年2月6日に第2回検討会を、本年3月19日に第3回検討会を開催し、本年3月27日付で「職場における心理的負荷評価表の見直し等に関する検討会報告書」を採択しました。この報告書によれば、「ストレス-脆弱性」理論に基づき策定された現行判断指針は、「合理性があり、労災認定の判断基準として妥当」とし、また現行判断指針の[別表1]の職場における心理的負荷評価表によるストレスの評価方法につき、「客観的評価を前提とした判断指針の考え方やシステムは合理的で妥当である」とし、しかし「職場環境の多様化等による、業務の集中化による心理的負荷、職場でのひどいいじめによる心理的負荷など、新たな心理的負荷が生ずる事案が認識されている現状にある」とし、「職場における心理的負荷表にかかる具体的出来事の追加又は修正」等につき、報告を行いました。その見直しは、職場における心理的負荷表の現行31項目から43項目に増加し、平均強度「III」の出来事として「ひどいいやがらせ、いじめ、又暴行を受けた」を一つ、平均強度「II」の出来事として「違法行為を強要された」、「自分の関係する仕事で多額の損失を出した」、「職場で顧客や取引先から無理な注文を受けた」、「達成困難なノルマを課された、「顧客や取引先からクレームを受けた」、「複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった」の六つの出来事を追加し、「部下とトラブルがあった」出来事一つを「I」から「II」に修正し、平均強度「1.」の出来事として六つの出来事を追加することが主たるものです。そして、この報告書に基づき、本年4月6日に判断指針の一部改正が行われました(基発第0406001号)。
しかし、今回の職場心理負荷評価表における「業務上の具体的出来事等に関する検証・検討」による現行判断指針の見直しでは、今日の深刻な過労自殺問題に適切に対応し、適正な労災補償を実施することはできず、制定後10年を経過しようとしている中で明らかとなった問題点につき、現行判断指針は、全面的に見直す必要があると考えます。
そこで、私たちは、従前御庁に提出した意見書を再度検討し、現行判断指針を全面的に見直し、今日の深刻な過労自殺問題に適切に対応し、適正な労災補償を実施できる判断指針を改定するよう下記のとおり意見を述べる次第です。
〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-17
過労死弁護団全国連絡会議 代表幹事 岡村 親宜
同 水野 幹男
同 松丸 正
記
第1 精神障害発症前に従事していた業務で遭遇した事件的出来事(ライフイべント)による「急性の心理的負荷」と相当因果関係の認められる精神障害の発症及びその精神障害による自殺のみを労災補償の対象とし、精神障害を発症し得る業務による心理的負荷と認定する評価基準を平均人基準とする現行判断指針を「基本的考え方」を改定し、精神障害発症・増悪前に従事していた「慢性及び急性の心理的負荷」と相当因果関係の認められる精神障害の発症・増悪及びその精神障害による自殺を労災補償の対象と認め、精神障害を発症・増悪し得る心理的負荷か否かにつき、同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準に評価するものとすること
1 現行判断指針の問題点
現行判断指針制定時に設置された労働省の「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」は、1999年7月29日付報告書を発表し、その「検討概要」において、職場における心理的負荷として、「ある出来事が起きたことが明確に認識される事実に係る」「急性ストレス」のみならず、「長時間労働、長く続く多忙、単調な孤独な繰り返し作業、単身赴任、交替勤務などのように持続的であり、継続される状況から生じる」「慢性ストレス」が存在していることを認め、業務による事件的出来事(ライフイべント)による「急性ストレス」の他に、「慢性ストレス」が精神障害発症の原因(環境からくるストレス)となることを認めながら、「検討結果」においては、精神障害の発症 原因としては、事件的出来事(ライフイベント)による急性の心理的負荷だけを取り上げ、「慢性の心理的負荷」を取り上げなかった。
その結果、現行判断指針では、発症前6か月間に、被災労働者が[別表1]の日常の労働生活でまれにしか遭遇しない非日常的な事件的出来事に遭遇し、しかもその事件的出来事による心理的負荷の強度が指針のIIないしIIIと評価され、かつ総合評価で「強」と評価されない限り、「業務上」とは認定されないとされている。
また、現行判断指針は、その「基本的考え方」において、「精神障害の業務上外の判断に当たり、「当該精神障害の発病に関与したと認められる業務による心理的負荷の強度の評価が重要である」とし、「その際、労災補償制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因となった出来事をどう受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めたかという客観的基準(平均人基準説)によって評価する必要がある」とし、判断要件として、平均人基準説により、「発病前6か月の間に客観的に当該精神障害を発病するおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること」が必要とした。
しかし、現行判断指針によれば、発症前6か月の期間に[別表1]の総合評価で、遭遇した出来事が「強」と認定されなければ、「業務以外の心理的負荷や個体側要因に特に問題がみられないときでも業務外とな」り、それは「『ストレス-脆弱性』理論によって形に現れない脆弱性という個体要因が本当の原因であると理解され」こととなってしまうが、これは、根本的に問題である。
2 トヨタ自動車事件・名古屋高裁平成15年7月8日判決
トヨタ自動車事件・名古屋高裁平成15年7月8日判決(労働判例856号)は、自動車の設計業務に従事していた被災者(係長)が、恒常的な時間外労働や残業規制による過密労働により、相当程度の心身的負荷を受けて精神的、肉体的疲労を蓄積していたところ、7月以降2車種の出図期限が重なったことにより、過重、過密な業務及び8月末期限の出図の遅れによる心理的負荷を受けていたものであるが、7月初旬頃労働組合の職場委員長に就任するよう要請され、何度も断ったが断りきれず同月下旬頃就任の承諾したものの、同委員長に就任することによる不安、焦燥の急性の心理的負荷が加わり、7月下旬ないし8月上旬頃うつ病を発症したが、8月初旬の過重、過密な業務及び出図期限の再延長による心理的負荷を受け、同月12日から同月17日までの夏休み期間中いくぶん疲労を回復したものの、夏休み明け後の開発プロジェクトの作業日程調整及び8月20日の南アフリカ共和国への16日間の出張命令による心理的負荷を受け、その後うつ病の症状を急激に悪化させ、同月26日、ビルから飛び降り自殺した事案につき、被災者のうつ病の発症と自殺には業務起因性が認められるとし、これを否定した豊田労基署長の遺族補償等不支給処分は違法とした。
この事案で問題となった発症前の心理的負荷は、被災者が7月以降に従事した2車種の出図期限が重なったことによる過密な設計業務及びこの2車種の8月末期限の出図の遅れにより受けた慢性の心理的負荷と、7月下旬頃職場委員長就任を承諾したことによる不安、焦燥の急性の心理的負荷の二つであり、これらの二つの心理的負荷が発症の原因となり得る心理的負荷と認められるか否かであった。そして問題となった発症後の心理的負荷は、夏休み明け後の開発プロジェクトの作業日程調整による慢性の心理的負荷と及び8月20日の南アリカ共和国への出張命令により受けた急性心理的負荷の二つであり、これらの心理的負荷が被災者のうつ病を増悪させる原因となり得る心理的負荷と認められるか否かであった。
厚生労働省は、この裁判において、指針制定時検討会座長の原田憲一らの医学意見書を提出し現行判断指針を適用すると、この事案は、(1)アジアカー、ライトエースの2車種の8月末出図期限、(2)職場委員長の就任承諾、(3)6か月後の南アフリカへの出張命令という三つの事件的出来事による心理的負荷が問題となるにすぎないとした。そして、(1)の出来事については、指針別表1の(1)の具体的出来事のいずれにも合致せず、どの出来事に近いかを類推すると、別表1の「ノルマが達成できなかった」に近い出来事となり、平均的心理負荷の強度は「II」であり、修正すべき視点で検討しても、作業自体は順調に進み、結果として完成をみており、期限付の作業は会社活動では日常的なことであるから、心理的負荷強度を修正する必要はなく、その心理的負荷強度は「I」に近い「II」と評価されるとした。そして前記(3)の出来事は、「組合業務は本来の業務とはいえないことから、業務による心理的負荷と評価するのは適切でない」とした。さらに、前記(3)の出来事は、「6か月先のことであり、被災者も承知しており、同人のキャリアからみて、特別過重な負荷と評価すべきではない」とした。その結果、この意見書は、発症の要因となる業務以外の心理的負荷は認められず、また、発症の要因と認められる個体側要因も認められないと認定しながら、「精神医学的経験則上、被災者の心理面の脆弱性が本件うつ病エピソードの発病の主な役割を果たした」ものであるとした。
これに対し、名古屋高裁判決は、発症前被災者が7月以降に従事した2車種の出図期限が重なったことによる過密な設計業務及びこの2車種の8月末期限の出図の遅れにより受けた慢性の心理的負荷につき、トヨタ自動車においては「設計業務の遅れは他の部署の日程にも大きな影響を及ぼすため、設計図の出図期限は遵守すべきものであるところ、先行試作設計の段階では」「出図期限の延期が認められたとしても、それは」「やむを得ず認められたものにすぎず、第1係長を統括する係長としてはマイナス評価を受けるおそれがあり、その後第1次試作設計の出図期限は遵守しなければならないのである」との理由で「極めて強い心理的負荷」であると認定した。
また、名古屋高裁判決は、7月下旬頃職場委員長就任を承諾したことによる不安、焦燥の心理的負荷につき、被災者が「悩んでいたのは、職場委員長の活動自体による不安ではなく、組合活動に時間と労力を取られることによって業務に当てる時間と労力が少なくなり、設計図の出図期限が遵 守出来なくなることに対する心配(不安、焦燥)であ」るから「業務上の出来事として取扱うのが相当」とし、その負荷は「当時も過重・過密な労働に従事し、さらに9月以降も過重・過密な労働に従事することの予定されていた被災者に対し、さらに強い心理的負荷を与えたと認められる」と認定した。
つぎに名古屋高裁判決は、夏休み明け後の開発プロジェクトの作業日程調整による心理的負荷につき、夏休み明け後の「8月18日から同月25日まで、被災者は、ライトエーストラックのコスト低減の問題検討、開発プロジェクトの作業日程調整及びライトエーストラックのリーフスプリング問題等の業務を遂行し、同月初旬に引き続き多忙であった」が、「そのような状況の下で、開発プロジェクトの作業日程調整は、被災者に対して、強い心理的負荷を与えた」と認定した。そして前記南アフリカ共和国出張命令により受けた急性の心理的負荷につき、本件出張命令は「6か月も先のことであったが、その予定日がアジアカーとライトエーストラックの第1次試作設計の出図時期と重なって」おり、被災者が「本件出張により上記出図時期が遵守できなくなるのではないかとの不安、焦燥を抱いたことは」「十分理解可能であるから、本件出張命令は、被災者に対し、強い心理的負荷を与え」た認められると認定した。
その上で、同判決は、被災者の「本件うつ病は、上記の、過重、過密な業務及び職場委員長への就任内定による心理的負荷と被災者のうつ病親和的性格(ただし、通常人の正常な範囲を逸脱するものではない)が相乗的に影響し合って発症した」ものであり、さらにその後の開発プロジェクトの作業日程調整及び本件出張命令(による心理的負荷)が「本件うつ病を急激に悪化させ、被災者は、本件うつ病の希死念慮の下に発作的に自殺したものと認めるのが相当であ」ると認定し、被災者の従事していた「業務と本件うつ病との間には相当因果関係を肯定することができ、本件自殺は、本件うつ病の症状としては発現したものである」と認定したのである。
そして、この事件は、行政機関は上告受理申立をせず、確定した。
この確定した司法判断に照らせば、発症前の事件的出来事による急性の心理的負荷を発症原因とする精神障害及びその精神障害による自殺を補償対象とする現行判断指針には、根本的に問題があることが明らかというべきである。
3 発病後の心理的負荷による増悪
これに対し、判断指針は、発病前の業務による心理的負荷を対象としており、発病後の心理的負荷は考慮していない。
精神医学上、軽症うつ病であっても自殺念慮は生じ得る。しかし、自殺事案において、何らかの心理的負荷(業務に限らない)によって精神障害を発病した労働者が、発病時点では正常な認識、行為選択能力が阻害されておらず、自殺を思いとどまる精神的な抑制力も阻害されていなかったが、発病後の業務による心理的負荷を受けて自殺を図った場合には、発病後の負荷により、精神障害が、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態にまで進行したと評価できるのであり、法的概念としての因果関係の判断に当たって、これを「うつ病の増悪」と評価したとしても、ある特定の事実(労働者が業務上の心理的負荷を受けたこと)が特定の結果(うつ病が増悪したこと)の発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することになるのであるから、法的判断として正当である。
日本ヘルス事件・大阪地裁平成19年11月12日判決(労働判例958号)は、「業務上の負荷によりうつ病を発症(ただし、その診断可能時点は必ずしも特定が容易とは言い難い。)した者が、未だ完全に行為選択能力や自殺を思いとどまる抑制力を失っていない状態において、改めて、社会通念上、うつ病を増悪させる程の業務上の負荷(通常人であっても、うつ病を発症する程度の心理的負荷)を受けた結果、希死念慮を高め、自殺を図った場合、相当因果関係を認めるのが合理的である場合が存する」と判示しており、この理を相当として認めているのである。
前記のとおり、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決は、うつ病の「増悪」も「発病」と同じ相当因果関係論で業務起因性を判断しており、海外出張による影響に対する不安、開発プロジェクトの作業日程調整は発症後のうつ病の増悪事由と判断した。同旨の裁判例は、九州カネライト事件・福岡高裁平成19年5月7日判決(労働判例943号)などがある。
本年に入って言い渡されたノヴァスペースデザイン事件・東京地裁平成21年3月18日判決は、「業務起因性を検討するに当たり、精神障害発症後の業務による心理的負荷を全く考慮しないのは相当でなく、精神障害発症による能力低下や易疲労性の増大等の精神障害発症後の状態を考慮に入れつつ、業務起因性を検討するのが相当である」と精神障害発病後の業務起因性について一般論を判示しており、近時の四国化工機工業事件・高松地裁平成21年2月9日判決、小田急レストランシステム事件・東京地裁平成21年5月20日判決及び日本トランスシティ事件・名古屋地裁平成21年5月28日判決も精神障害発病後の心理的負荷を考慮しているのであって、これが近時の裁判例の主流になっている。
このように裁判例は、精神障害の発病について業務起因性が認められるか否かを問わず、精神障害発病後の業務による心理的負荷により精神障害が「増悪」した場合の業務起因性を認めているものである。
また、うつ病の生存事案であり、解雇の効力、未払賃金請求権や安全配慮義務違反等に基づく損害賠償責任が争われた、東芝事件・東京地裁平成20年4月22日判決(労働判例965号)は、「原告が平成13年4月にうつ病を発症し、同年8月ころまでに症状が増悪していったのは、被告が、原告の業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうことがないような配慮をしない債務不履行によるものであるということができる」と判示しており、自殺に至らなかった精神障害事案において明確に発症後の業務上の心理的負荷による症状増悪を認めている。デンソー(トヨタ自動車)事件・名古屋地裁平成20年10月30日判決(労働判例978号)も同旨である。
以上の裁判例の傾向からすれば、発病後の業務による心理的負荷を考慮しない判断指針の「基本的考え方」は速やかに改定されるべきである。
4 慢性ストレスの評価
今日、医学上、精神障害は、素因、環境因(身体因、心因)の複数の病因が関与して発症しており、環境からの心理的負荷と個体側の反応性、脆弱性との相関関係で精神破綻が生じて発症する(「ストレス-脆弱性」理論)と理解されているが、精神障害の発症原因となる「環境からくるストレス」には、その人生でたまにしか遭遇しない事件的出来事(ライフイベント)による急性の心理的負荷よりも、むしろ日常生活において生ずる混乱や落ち込みの長期間の日常的煩わしさ(ディリー・ハッスルズ)である持続的な「慢性の心理的負荷」が精神障害の発症・増悪に作用しているとされているのである。
そして、現行判断指針制定時の検討会座長の原田憲一元東京大学教授自身、指針制定後、「ライフイベント(急性ストレス)より持続的、日常的なストレス(慢性ストレス)の方が精神的健康にはるかに害があることは、Bleuler,E.を挙げるまでもなく精神医学の常識である」と指摘し(「精神に関わる労災認定の考え方と実際上の問題点」精神科治療学22(1);69-75、2007)、また、「職業連関の心理的ストレスとして検討会が取り上げた出来事は急性、1回性のストレスが多い。Bleulerがその精神医学教科書の中で強調しているように、精神発達に悪影響を与えるのは1回性の出来事よりも持続的な慢性の感情緊張である。慢性・持続性の日常的なストレスの方がしばしば精神健康に有害であることは、Lazarusや夏目(夏目誠「ストレス強度と対応」産業精神保健2000:8:17-23)が指摘している」と述べ、「慢性・持続性ストレス」は「今後に残されている問題」であるとしているところである(原田憲「精神障害の労災認定」産業精神保健8(4):275-279:2000)。
また、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決、九州カネライト事件・福岡高裁判決、中部電力事件・名古屋高裁平成19年10月31日判決(労働判例954号)など多くの裁判例は、出来事に伴う変化の場面で慢性ストレスを評価しているのではなく、出来事発生以前から発生後、さらには精神障害発病後に至るまで、あらゆる段階において慢性ストレスを評価しているものである。
とすれば、判断指針が出来事に伴う変化の場面で慢性ストレスを評価しているとしても、そうであるからといって、判断指針の欠陥を修補するものではない。
したがって、精神障害の発症原因として、「急性の心理的負荷」だけを発症原因と認め、この発症前に従事していた業務により遭遇した「急性の心理的負荷」と相当因果関係のある精神障害の発症及びその精神障害による自殺についてのみ「業務上」の疾病及び「業務上」の死亡と取り扱うとし、労働者が日常の労働生活により「慢性の心理的負荷」と相当因果関係のある精神障害の発症・増悪及びその精神障害による自殺を「業務上」の疾病及び「業務上」の死亡と認めない現行判断指針は、今日の精神医学の常識に反しており、現行判断指針のこの「基本的考え方」を改定し、前記精神障害発症の機序を前提とし、被災者が精神障害発症・増悪の原因となる業務による「慢性及び急性の心理的負荷」と被災者の当該精神障害の発症・増悪及び当該精神障害による自殺との間には相当因果関係が認められれぱ、「業務上」の疾病及び「業務上」の死亡と取り扱うことを明確に定めるのが相当というべきである。
5 過重負荷評価基準
トヨタ自動車事件・名古屋地裁平成13年6月18日判決(労働判例814号)は、過重負荷評価基準を「同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で、業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし、同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者)をと」し、「同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準とするということは、被災労働者の性格傾向が同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、当該被災労働者を基準と」するのが相当とした(判決書104頁。平均的労働者最下限基準説)。この控訴審である名古屋高裁判決は、「報告書を取りまとめた委員会の座長を務めた原田憲一医師の当審における供述及び陳述書(乙第25号証)によれば、通常想定される範囲の同種労働者の中で最も脆弱な者を基準にするという考え方は、専門検討会や判断指針と共通するものであると認められる。さらに、控訴人(豊田労基署長)の主張する平均人基準説も、平均人としてどのような者を想定しているのかが必ずしも明らかではなく、平均という言葉が全体の2分の1程度の水準を意味するものと理解することも可能ではあるが、判断指針と同程度の水準を想定しているのであれば、上記(1)の見解(地裁判決)と大差はないものと考えられる」(判決書50頁)と判示し、実質的に原審名古屋地裁判決が判示した基準を是認したものである。同旨の裁判例は、中部電力事件・名古屋地裁平成18年5月17日判決(労働判例918号)、四国化工機工業事件・高松地裁判決などがある。
また、中部電力事件・名古屋高裁判決は、同種労働者ないし平均的労働者を基準にしながらも、その労働者群の中に「相対的に適応能力、ストレス適所能力の低いものも含む」と判示しており、また、九州カネライト事件・福岡高裁判決は、「同種の労働者という概念は、通常想定される労働者の多様さの範囲において、心理的負荷となり得る出来事等の受け止め方に幅があることを前提とした概念であることを考慮する必要がある」と判示し、しかもこの福岡高裁判決は、「原田意見書が『通常想定される範囲の同種労働者の中で脆弱な者を含んでの基準』が正確である旨を指摘するとおり、平均的労働者の範囲にも幅があり、当該労働者の個体側要因も多様で、その脆弱性も雇用関係のもとで築かれる場合もあるから、相対的な比較によりその軽重あるいは因果関係の存在が判断されるのが相当な場合もあるというべきである」と原審福岡地裁判決(労働判例916号)の判示を補充している。これらの裁判例の判示からすれば、平均的労働者最下限基準説と異ならないと考えられる。
ところで、最高裁判所事務総局が発行した、労働関係民事行政裁判資料第41号「労働者災害補償関係事件執務資料」(1997年3月。以下「執務資料」という。)は、平均的な労働者、すなわち通常の勤務に就くことが期待されている者を基準とするという見解を紹介している。執務資料によれば、「通常の勤務に就くことが期待されている者とは、完全な健康体の者のほかに、基礎疾病を有するものの勤務の軽減を要せず通常の勤務に就き得る者、いわば平均的労働者の最下限の者も含む」という。そして、「この考え方によると、基礎疾病を有しながら通常の勤務に就いている者にとって、その基礎疾病を有意に悪化させる可能性のある業務は危険を内在化したものであり、そのような業務に就いたことにより基礎疾病が有意に悪化した場合には、業務とその結果との間には相当因果関係を肯定し得ることとなる。すなわち、平均的労働者の範ちゅうに属する者については、条件関係さえ肯定できれば、業務起因性を肯定し得ることにな」る。また、「平均的労働者の範ちゅうに属さない者(例えば、基礎疾病を有するために勤務の制限を受けている者)も、一切救済されないわけではなく、その従事した業務が平均的労働者の最下限の者にとっても危険と評価し得るものであり、かつ、条件関係が肯定できれば、相当因果関係を認めることができるものである」(9頁)。
トヨタ自動車事件・名古屋地裁判決を始めとする前記各裁判例及び執務資料の見解(平均的労働者最下限基準説)を採用するのであれば、精神障害発病により勤務制限を受けている労働者の救済はある程度可能となる。
これに対し、判断指針は平均人を基準としており、以上の各判決により国側が多数敗訴しているにもかかわらず、厚生労働省はこの説に固執している。
そればかりか、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決が言い渡されて国側の敗訴が確定した直後の2003年7月31日、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長名義で「精神障害等事案の高裁判決に係る留意事項について」と題する通知(基労補第0731001号)を発した。この通知は、名古屋高裁判決が「判断指針の合理性を認め、また、心理的負荷の強度の評価についても、本人を基準として判断する考えを明確に否定するとともに、最も脆弱である者を基準として判断すべきものとはしていないと理解でき、国の主張が容れられたものとなっている」と評している。しかしながら、名古屋高裁判決は、判断指針の「一定の合理性」を認めながらも、「当該労働者が置かれた具体的な立場や状況などを十分斟酌して適正に心理的負荷の強度を評価するに足りるだけの明確な基準になっているとするには、いまだ十分とはいえず、うつ病の業務起因性が争われた訴訟において、この基準のみをもって判断するのが相当であるとまではいえない」と判示しているのであり、単純に「判断指針の合理性を認め」たという評価は誤りであり、名古屋高裁判決が平均的労働者最下限基準説を否定したというのも前記のとおり誤りである。
しかも、九州カネライト事件・福岡高裁判決は、「被告の主張は、同種労働者の多様性の一つとして太郎が有する属性、性格を捨象し、同種労働者の範囲を限定的に解する点において前提を誤っている上、複数の心理的負荷の要因の総合的な検討も十分でないから、採用できない」と、判断指針の過重負荷評価基準を批判しているところである。
このように厚生労働省は、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決を我田引水に解釈し、過重負荷評価基準を厳格にして被災労働者及びその遺族の救済の範囲を狭めている。
しかしながら、平均人に「ストレス耐性の低い者」を含めるとしても、前掲原田・精神科治療学22巻1号が、「『平均人』とは、通常想定される多様性の範囲内で、ストレスに強い人も弱い人も含めた労働者群を指す」と解説するとおり、平均人には最下限の者も含むとして幅のあるものとして捉えざるを得ないのである。
6 被災労働者本人の立場や状況の考慮
トヨタ自動車事件・名古屋地裁判決は、「亡太郎にはこれまでの生活史を通じて社会適応状況に特別の問題はなく、うつ病親和的な性格ではあったが、正常人の通常の範囲を逸脱しているものではなく、模範的で優秀な技術者であったのであるから、亡太郎の性格傾向は、同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでなかったと認められる」から、「本件においては、亡太郎を基準として、当該業務がうつ病を発症させる危険性があったか否かを判断すればよいことになる」と判示しており、「限りなく本人基準に近い判断を示している」と評されている。また、この控訴審の名古屋高裁判決は、このような判示をしていないものの、「ストレスの性質上、本人が置かれた立場や状況を充分斟酌して出来事のもつ意味合いを把握した上で、ストレスの強度を客観的見地から評価することが必要であり、本件においては、亡太郎が従事していた業務が、自動車製造における日本のトップ企業において、内容が高度で専門的であり、かつ、生産効率を重視した会社の方針に基づき高い労働密度の業務であると認められる中で、いわゆる会社人間として仕事優先の生活をして、第1係係長という中間管理職として恒常的に時間外労働を行ってきた実情を踏まえて判断する必要がある」と判示し、被災労働者本人の有する実情を考慮している。中部電力事件・名古屋高裁判決も同旨である。
「『人』は本来的に多様であるから、精神障害の労災認定において客観性を強調することは具体的妥当性を逸することになる」(石田信平「過労自殺の業務上外認定について」(同志社法学57巻7号)144頁)という指摘は、裁判例の考え方の背景にあるものといえる。
したがって、判断指針は、本人が置かれた立場や状況を充分斟酌して出来事のもつ意味合いを把握した上で業務による心理的負荷を評価するよう改定すべきである。
これに対し、前出の補償課長通知は、判断指針に「既に盛り込まれている」と述べている。しかし、「心理的負荷の強度を修正する視点」は当該出来事自体の程度やそれに付随又は関連する事項に着眼するというにすぎず、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決が判示するような、必ずしも「出来事」とまでは評価されないが慢性ストレスを生み出す企業体質、業務・職種・役位の内容や性質、就労実態などの実質を反映されるものとはなっていない。厚生労働省は、名古屋高裁判決が提起した判断指針の問題点を正解していないのであり、改定の必要性があるのである。
したがって、精神障害の発症・増悪に関与したと認められる慢性及び急性の心理的負荷が、精神障害を発症・増悪し得る程度の心理的負荷であるか否かの評価基準は、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決が判示しているとおり、「ストレスの性質上、本人の置かれた立場や状況を充分斟酌して」「ストレスの強度を客観的見地から評価することが必要」であり、それは、被災労働者とその遺家族の人間に値する生活を充たすための必要最小限度の法定補償を迅速、公平に行うことを目的とする労災補償制度の目的に照らし、「同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で、業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし、同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者)を基準」とするのが相当というべきである。
第2 精神障害発症前6か月間に、その発症の原因となり得る急性の心理的負荷の業務に従事していた場合にだけ「業務上」と認定する現行判断指針の判断要件を改定し、精神障害の発症・増悪前1年間に、精神障害の発症・増悪の原因となり得る慢性及び急性の心理的負荷の認められる業務に従事していた場合には、「業務上」と認定できる判断要件とすること
現行判断指針は、精神障害の発症につき、発症前6か月間に、被災者が「別表1]の職場の心理負荷評価表の日常の労働生活でまれにしか遭遇しない非日常的な事件的出来事に遭遇し、しかもその事件的出来事による心理的負荷の強度が、指針の修正する視点で評価して、IIないしIIIと評価され、かつ総合評価で「強」と評価されない限り「業務上」とは認定されないとしている。
そして現行判断指針は、その例外的場合として、慢性的な心理的負荷につき、
(1) 「業務上の傷病により 6か月を超えて療養中に発病した精神障害」については「病状が急変し極度の苦痛をともなった場合など」「生死にかかわ」りその「心理的負荷が極度のもの」、
(2) 「極度の長時間労働」、「例えば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し、それ事態がうつ病の発症のおそれのあるもの」、
に限り、精神障害発症の原因となり得る心理的負荷となるとしている。
しかし、前記のとおり、今日の精神医学では、精神障害は、事件的出来事(ライフイベント)による「急性の心理的負荷」よりも、むしろ長期間の日常生活において生ずる「慢性の心理的負荷」が精神障害の発症・増悪に作用しているとされており、しかも、「慢性の心理的負荷」が原因となって発症する精神障害は、現行判断指針がその例外として認めている「業務上の傷病により6か月を超えて療養中に発病した精神障害」及び「極度の長時間労働」による精神障害に限定し、しかも「生死にかかわ」り、その「心理的負荷が極度」の長期入院でなければならず、「数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保でき」ず、「心身の極度の疲弊、消耗をし」た長時間労働でなければ精神障害発症の原因となり得る心理的負荷とはならないとする医学上の根拠は全くないというべきである。
そこで、この根本問題を解決し、被災者が精神障害を発症・増悪させる前に従事していた業務において遭遇した「慢性及び急性の心理的負荷」と、当該精神障害の発症・増悪及びその精神障害による自殺との間に相当因果関係が認められれば、「業務上」の疾病及び「業務上」の死亡と認定するため、現行判断指針の判断要件を改定し、下記の3つの要件に該当する精神精神障害及びその精神障害による自殺は、労働基準法施行規則別表第1の2の第9号に該当する『業務上の疾病もしくは死亡として取り扱うことするのが相当というべきである。
(1) 被災者に個体側原因(既往歴、社会適応状況、アルコール等依存状況、性格傾向)があり、これが原因となって精神障害を発病、増悪又は自殺させた場合、被災者の個体側原因が、当該業務に従事する以前に、確たる因子がなくても自然経過により精神障害を発病又は増悪させる寸前にまで進行していたとは認められないこと。
(2) 被災者が従事した当該業務による慢性及び急性の心理的負荷が、同人の個体側原因をその自然経過を超えて、精神障害を発病、増悪又は自殺させる要因となり得るものと認められること。
(3) 被災者の従事した当該業務以外に、同人の個体側原因をその自然経過を超えて、精神障害を発病、増悪又は自殺させる原因となる確たる因子が認められないこと。
この場合、急性の心理的負荷のみならず慢性の心理的負荷を対象とし、かつ発症後業務に従事したことによる精神障害の増悪の原因となり得る心理的負荷をも対象とする関係上、対象とする心理的負荷は、精神障害を発症・増悪する前1年間とするのが相当というべきである(「精神障害と労災研究会」(代表:精神科医天笠崇)の「平成17年度研究報告書」参照)。
第3 業務による精神障害を発症・増悪し得る心理的負荷の評価方法につき、現行判断指針の[別表1]の職場における心理的負荷表による個別的出来事毎の当てはめにより、総合評価で「強」と認定出来なければ精神障害発症の原因となり得る心理的負荷とは認められないとする心理的負荷の強度の評価方法を改定し、個別事案毎に、被災者が精神障害を発症・増悪させる前1年間に遭遇した慢性及び急性の心理的負荷を総合し、被災者の置かれた立場や状況を十分斟酌し、その全体の心理的負荷が、経験則上、被災者と同種労働者の中で、その性格傾向が最も脆弱な者を基準して評価し、精神障害の発症・増悪の原因となり得る心理的負荷と認定できるか否かを認定する評価方法を採用すること
1 判断指針の問題点
現行判断指針は、業務による精神障害を発症し得る心理的負荷の評価方法につき、(1)まず、[別表1]の心理的負荷評価表の(1)により、被災者が精神障害発症前に遭遇した個々の事件的出来事が、同表のいずれの出来事に該当するかの当てはめを行ってそれが同表の平均的心理的負荷の強度が、I、II、IIIいずれかを認定し、(2)つぎに、同表の(2)の「心理的負荷を修正する視点」で検討して、その強度がI、II、IIIのどの強度かを認定し、(3)そして(3)の「出来事後の状況が持続する程度を検討する視点」欄記載の視点から「出来事に伴う変化等はその後どの程度持続、拡大あるいは改善したか」について総合評価するとし、その総合評価で、出来事が下記ア及びイの場合だけ、精神障害の発症の原因となり得る心理的負荷である「強」と認定し、そうでない場合は「強」と認定しないという評価方法を採用している。
ア 上記(2)の評価でIIIと評価され、かつ上記(3)の評価で「相当程度過重(同種労働者と比較して業務内容が困難で、業務量も過大であると認められる状態)であると認められる場合
イ 上記(2)の評価でIIと評価され、かつ上記(3)の評価で「特に過重(同種労働者と比較して業務内容が困難で、恒常的な長時間労働が認められ、かつ過大な責任の発生・支援・協力の欠如等特に困難な状況が認められる状態)であると認められる場合
しかも、現行判断指針は、被災者が遭遇した出来事が複数あっても、これら複数の出来事を個別に評価し、複数の出来事による心理的負荷を総合して全体として精神障害発症の原因となり得る心理的負荷が否かの評価方法を採用していいない。
しかし、この平均人基準説を採る現行判断指針による心理的負荷の強度の評価方法は、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決が判示しているとおり、「判断指針は、現在の医学知見に沿って作成されたもので、一定の合理性があることは認められるものの、当てはめや評価にあたって幅のある判断を加えて行うものであるところ、当該労働者が置かれた具体的な立場や状況などを充分斟酌して適正に心理的負荷の強度を評価するに足りるだけの明確な基準になっているとするには、未だ十分とはいえ」ないというべきであり、現行判断指針の[別表1]による当てはめにより「強」と認定されない限り、精神障害発症の原因となり得る心理的負荷とは認められないとすることは、極めて不相当というべきである。
2 九州カネライト事件・福岡高裁平成19年5月7日判決
九州カネライト事件・福岡高裁判決は、長年鐘化工業(株)に勤務し、食品関係の設備設計業務に従事し、機械のメンテナンス業務に従事したことのなかった兵庫県内に家族と居住していた被災者(満48歳)が、平成11年8月2日付で鐘化工業(株)の子会社である福岡県築後市所在の発泡ポリエスチレンを素材としたボード、建材及び畳芯の製造・加工・販売を事業とする九州カネライト(株)へ出向を命じられ、同年12月末に退職予定の設備係長一人の同社設備係に配属され、会社から自転車で10分弱の距離にある会社借り上げのワンルームマンションに居住して、同係長から設備係の業務の引継を受けていたところ、同年10月下旬頃から11月頃にかけて「適応障害」または「うつ病」を発症し、同年12月15日、自殺した事案につき、八女労基署長の遺族補償等不支給処分の取消を命じた一審判決を認め、行政機関の控訴を棄却した。
この事案につき、厚生労働省は、「現在の精神医学のレベルにおいて、個体側の脆弱性を抽出し、客観的に測定するのは困難であり、平均的な労働者の受け止め方を基準として、出来事自体の有する精神障害を招く危険性を判断すべきで、ライフイベント法等に基づいた判断指針は合理性がある」と主張した。そして、本件で問題となる出来事は、「出向した」と「仕事内容に変化があった」の二つであるとし、「出向があった」は、その平均強度は「II」であり、同人の出向は「未知の分野への職種変換を伴うものでもなく、宿舎の決定においても本人の希望が尊重されており」、「設備係長からの引き継ぎを終えた後は設備課長への昇進が予定されていた」ものであり、「不利益な取り扱い」ではないから、修正する視点により平均強度「II」は修正されず、総合評価で被災者が精神障害を発症し得る心理的負荷である「強」とは評価されない旨主張した。
また、「仕事内容に大きな変化があった」出来事は、[別表1」によりその平均強度は「II」であり、被災者の「本件出向後の業務内容も特に過大、困難なものであったとはいえなかった」から、これを「III」に修正すべき理由はなく、出向後に従事した業務による心理的負荷は、同人の精神障害を発症させるおそれのある「強」と評価される心理的負荷であったとはいえない旨主張した。
これに対し、福岡高裁判決は、「特に、心理的負荷の要因となる業務上の出来事が複数存在する場合には、各要因が相互に関連して一体となって精神障害の発症に寄与すると考えられるから、これらの出来事を総合的に判断し、精神障害を発症させるおそれのある強度のものであるかを具体的に総合判断するのが相当である」と判示した。そして、同判決の引用する一審判決が「心理的負荷の要因となる業務上の出来事が複数存在する場合においては、それらの要因は相互に関連し、一体となって精神障害の発症に寄与するものであるから、個々の出来事の心理的負荷ではなく、これらを総合的に判断して、精神障害を発症させるおそれのある強度のものであるかを検討する必要があ」り、また、労働者の経歴、職歴、職場における立場、性格等によって、心理的負荷の要因となり得る出来事等の受け止め方に差があることは明らかであるから、心理的負荷の強度を検討するにあたっては、当該労働者の経歴、職歴、職場における立場、性格等を考慮する必要があ」るとの判示を引用した。
そして、福岡高裁判決の引用する一審判決は、被災者は「住み慣れた関西地方を離れ、単身赴任を余儀なくされたこと、担当業務も長年従事していた機械設備の設計管理業務から機械設備の保全業務に変わったこと、本件出向前には細分化されたグループでの専門的業務を担当していたのに対し、引き継ぎ終了後は一人でカネライトの機械設備の保全の全てを行うという広範な業務を担当する予定となっていたことが認められ、本件出向により、相当の心理的負荷を受けたといえる」と認定した。また、被災者は「本件出向前に従事していた機械設備の設計業務には、長い期間にわたる経験を持ち、ある程度の自信をもっていたにもかかわらず、本件出向後は、ほとんど未経験の分野である保全業務に従事することとなったと認められ、その業務は、被災者の手指の障害があることからも」被災者にとって「不安の大きい分野であったといえるから、業務それ自体から受ける心理的負荷も、従前の業務内容に比べ、大きかったといえる」とした。
そして、「さらに被災者は、保全業務の引き継ぎと平行して、新規機械の導入や、ISO認証取得のための業務にも従事したことにより、保全業務の引き継ぎのみに集中できる状況になく、技術の習得も周囲の期待していたようには進まず、そのため」「9月につき46時間58分、10月につき76時間38分、11月につき88時間20分」、「会社に残って引継ぎ内容の確認、資料作成等を行った」が、被災者が「本件出向前にほとんど時間外労働をしていなかったことに照らせば、その心理的負荷は大きかった」と認定し、被災者は「鐘化工業に入社して以来、出向の経験も転勤の経験もなく」、「業務内容の大きな変更も本件出向までなかったこと、被災者は真面目で内向的であり、仕事は自分で抱え込む性格であったこと、本件出向前にはほとんど時間外労働はなかったことが認められ」、「以上の被災者の経歴及び性格を前提とすれば」、「本件出向後、短期間の間に複数の心理的負荷の要因あったことを含めて、被災者が受けた業務による心理的負荷を総合的に判断すれば、業務による心理的負荷は、被災者と同種労働者にとって精神障害を発症させるおそれのある心理的負荷であったといえる」と判示しているところである。
この高裁判決は、この事案において、精神障害発症前に、被災者らは出向という出来事による急性の心理的負荷、出向後カネライトで従事した係長から引継ぎを受けていた機械の保全業務による慢性の心理的負荷、引継ぎの保全業務と平行して従事した新機械導入やISO認証取得のために従事した業務により引き継ぎ業務ができず、そのため時間外労働を行ったことによる慢性の心理的負荷につき、これらの心理的負荷を総合し、これら複数の心理的負荷が全体として精神障害発症の原因となり得る心理的負荷と認定したものである。
厚生労働省は、上告受理申立をせず、確定した。
3 ストレスの相乗効果の評価
前記のとおり、九州カネライト事件・福岡高裁判決は、「心理的負荷の要因となる業務上の出来事が複数存在する場合には、各要因が相互に関連して一体となって精神障害の発症に寄与すると考えられるから、これらの出来事を総合的に判断し、精神障害を発症させるおそれのある強度のものであるかを具体的かつ総合的に判断するのが相当である」と判示している。同旨の裁判例は、トヨタ自動車事件・名古屋高裁判決、中部電力事件・名古屋高裁判決、日本ヘルス工業事件・大阪地裁判決、小田急レストランシステム事件・東京地裁平成21年5月20日判決など多数ある。
これに対し、判断指針は、「出来事」(=災害)中心主義であり、強度Iの出来事がいくつあっても心理的負荷の強度がIIにはならず、強度IIがいくつあっても強度IIIにはならない。この点につき、九州カネライト事件・福岡高裁判決は、「基準に対する当てはめや評価に当たっては、判断者の裁量の幅が広いこと、また、各出来事に対する心理的負荷の判定を基礎としており、各出来事相互間の関係、相乗効果等を評価する視点が十分でないことからすれば、この基準のみをもって、精神障害の業務起因性が判断されるべきものとはいえ」ないと批判している。九州テン事件・福岡地裁平成19年6月27日判決(労働判例944号)も同旨である。
この確定した司法判断に照らせば、精神障害発症・増悪の原因となり得る心理的負荷の強度の評価方法は、現行判断指針の[別表1]によるのは相当ではなく、これを改定し、事案毎に、当該労働者が置かれた立場や状況を十分斟酌して、発症・増悪前おおむね1年間に従事していた業務による慢性及び急性の心理的負荷を対象とし、この間に被災労働者が業務により遭遇した「慢性及び急性の心理的負荷」の全てを総合し、被災者の置かれた立場や状況を十分斟酌し、その全体の心理的負荷が、経験則上、被災者と同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし、被災者の性格傾向が同種労働者の性格傾向として通常想定される者)を基準にして認定する方法を採用するのが相当というべきである。現行判断指針の[別表1]の職場における心理的負荷評価表は、この精神障害発症・増悪の原因となり得る心理的負荷の評価方法の一資料となり得るが、この認定の評価方法とはなり得ないというべきである。
なお、この認定において、トヨタ自動車事件・名古屋地裁判決が判示しているとおり、「被災労働者の性格傾向が同種労者の性格傾向の多さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、当該被災労働者を基準として」評価するのが相当というべきである。
第4 長時間労働による慢性の心理的負荷による精神障害の発症につき、現行判断指針の「極度の長時間労働、例えば数週間にわたり生理的に必要最小限度の睡眠時間を確保できないなどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し」た場合にだけに限定して精神障害発症の原因となり得る心理的負荷と認める現行判断指針を改定し、1週間当たり40時間を超えて労働した時間外労働時間が、発症前1か月当たり100時間、または発症前2か月ないし6か月間にわたり1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働に従事していた場合には、この長時間労働単独で精神障害発症の原因となり得る心理的負荷と認めるものとすること
現行判断指針は、精神障害発症の原因となり得る心理的負荷につき、事件的出来事による急性の心理的負荷を対象とし、慢性の心理的負荷をその対象としていないが、その例外として、指針[別表1]の(3)の業務による心理的負荷の強度を「強」とする特別の出来事として、「極度の長時間労働、例えば数週間にわたり生理的に必要最小限度の睡眠時間を確保できないなどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し、それ自体がうつ病等の発病原因と認められるもの」については、[別表1]の心理的負荷評価方法により「強」と認められなくとも、心理的負荷の強度を「強」とすることができるとし、この「極度の長時間労働」による慢性の心理的負荷に限り、精神障害発症の原因となり得る心理的負荷となることを認めている。
しかし、2001年12月12日に制定された「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(基発第1063号)は、脳・心臓疾患発症の原因となり得る過重負荷として、1週間当たり40時間を超えて労働した時間外労働時間が、発症前1か月当たり100時間、又は発症前2か月ないし6か月間にわたり1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働に従事していた場合には、その心理的負荷単独で脳・心臓疾患発症の原因となり得る過重負荷と認めているところである。それは、このような長時間労働は、労働の質的過重性を度外視しても、それ単独で人間が生理的に必要とする睡眠時間を奪い、その負荷が長期間にわたり作用し疲労の蓄積が生じ、これが血管病変等をその自然経過を著しく超えて増悪させ、脳・心臓疾患を発症させる蓋然性が高いとされているからである。このことは、精神障害の発症についても同様であり、このような長時間労働は、労働の質的過重性を度外視しても、人間が生理的に必要とする睡眠時間を奪い、その負荷が長期間にわたり作用し、疲労の蓄積が生じ、これが心理的負荷を増大させ、精神障害を発症させる蓋然性が高いというべきである。そして、現に、日本産業精神保健学会理事長高田勗「平成15年度委託研究報告書I精神疾患発症と長時間残業との因果関係に関する研究」(主任研究者黒木宣夫東邦大学佐倉病院精神医学研究室。2004年3月)の報告書は、その研究により、「長時間残業による睡眠不足が精神疾患発症に関連があることは疑う余地もなく、特に長時間残業が月間100時間を超えるとそれ以下の長時間残業よりも精神疾患発症が早まるとの結論が得られた」と報告しているところである。
したがって、極度の長時間労働にる慢性の心理的負荷に限り、精神障害発症の原因となり得る心理的負荷と認めるとの現行判断指針を改定し、過労性脳・心臓疾患の認定基準と同様、1週間当たり40時間を超えて労働した時間外労働時間が、発症前1か月当たり100時間、または発症前2か月ないし6か月間にわたり1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働に従事していた場合には、その心理的負荷単独で、精神障害発症の原因となり得る心理的負荷と認めるものとするのが相当というべきである。
以上
[表] 精神障害・自殺労災判断指針改定案(2009年)
第1 基本的な考え方
精神障害は、今日現在、医学上、単一の病因ではなく、素因、環境因(身体因、心因)の複 数の病因が関与しており、環境からくる心理的負荷と個体側の反応性、脆弱性の相関関係で精神破綻が生じて発症するとされている(「ストレス-脆弱性」理論)。そして、この環境からくる心理的負荷には、患者がその人生でたまにしか遭遇しない事件的出来事による急性の心理的負荷よりも、むしろ日常生活において長期間に生ずる混乱や落ち込みのディリー・ハッスルズ(日常的煩わしさ)と言われている持続的な慢性の心理的負荷が精神障害の発症・憎悪の原因として作用しているとされている。
本判断指針は、この精神障害の発症機序を前提にして、被災労働者の精神障害発症・増悪前に従事していた業務による「慢性及び急性の心理的負荷」と同人に発症・増悪した精神障害及びその精神障害による自殺との間に相当因果関係が認められれば、「業務上」の疾病及び「業務上」の死亡と取り扱うものである。
ところで、この「業務上」外の判断おいては、精神障害の発症・増悪に関与した慢性及び急性の心理的負荷の強度が、被災者の精神障害を発症・増悪させ得る程度の心理的負荷と認められるかどうかの判断が重要である。この判断につき、本判断指針は、被災労働者とその遺家族の人間に値する生活を充たす最低限度の法定補償を迅速、公平に行うとの労災補償制度の目的に照らし、多くの人々がどう受け止めたかの平均人基準説によることなく、被災者と同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準に、被災者が、精神障害の発症・増悪の前に精神障害の発症・増悪となり得る慢性及び急性の心理的負荷の認められる業務に従事していたか否かを判断するものとする。
また、この「業務上」外の判断おいては、被災者が、業務以外の心理的負荷が原因で精神障害を発症・増悪させたか否かを判断する必要がある。
さらに、この「業務上」外の判断おいては、被災者には、他に精神障害を発症・増悪させる個体側原因があったか否かを判断する必要がある。
そこで、労災請求事案に処理に当たっては、被災者の精神障害発症・増悪の有無及びその時期を判断し、被災者の精神障害は、精神障害発症・増悪の原因となり得る心理的負荷の認められる業務に従事していたか否か、被災者は業務以外の心理的負荷が原因で精神障害を発症・増悪したと認められるか否か、被災者には他に精神障害を発症・増悪させる確たる個体側原因は認められるか否かにつき総合的に検討し、これらの事実を総合して、被災者の精神障害の発症・増悪及びその精神障害による自殺が、「業務上」の疾病及び「業務上」の死亡に該当するか否かを判断することとするものである。
第2 対象疾病について
本判断指針は、WHOのICD-10の第V章に分類されている全ての精神障害を対象疾病として取り扱うものとする。
第3 判断要件について
下記の1、2及び3の要件を満たす精神障害の発症・増悪及びその精神障害による自殺は、労働基準法施行規則別表第1の2の第9号に該当する「業務上」の疾病及び「業務上」の死亡として取り扱うものする。
- 被災者に個体側原因(既往歴、社会適応状況、アルコール等依存状況、性格傾向)があり、これが原因となって精神障害を発病、増悪又は自殺させた場合、被災者の個体側原因が、当該業務に従事する以前に、確たる因子がなくても自然経過により精神障害を発病又は増悪させる寸前にまで進行していたとは認められないこと。
- 被災者が従事した当該業務による慢性及び急性の心理的負荷が、同人の個体側原因をその自然経過を超えて、精神障害を発病、増悪又は自殺させる要因となり得るものと認められること。
- 被災者の従事した当該業務以外に、同人の個体側原因をその自然経過を超えて、精神障害を発病、増悪又は自殺させる原因となる確たる因子が認められないこと。
第4 判断指針の運用基準について
1 精神障害発症の有無、病名及び発症時期の特定について
精神障害の発症の有無、病名、発症時期及び増悪の有無とその時期は、業務と発症・増悪との関連性を検討する際の起点となる重要な事実であり、被災者本人の日記・メモ等の情報、治療歴のある場合はその情報、治療歴のない場合は関係者からの報告書、聴取書等の情報、その他の情報を総合し、ICD-10診断ガイドラインの診断基準に照らして特定するものとする。なお、この場合、治療歴がなく、もしくは発症後相当期間を経過して治療を開始し、情報が少なく診断基準を充たす事実が十分に確認できなくても、合理的に推定して特定して差しつかえないものとする。
2 判断要件の1の「慢性及び急性の心理的過重負荷」について
ア 「慢性及び急性の心理的負荷」とは、経験則に照らし、精神障害発症・増悪の原因となり得る慢性及び急性の心理的負荷をいう。
イ 被災者が、精神障害を発症し、引き続き業務に従事した場合は、業務従事の最終日前おおむね1年間に従事した業務を対象とし、その間に被災者が遭遇した慢性及び急性の心理的負荷が、精神障害の発症・増悪の原因となり得る「慢性及び急性の心理的負荷」と認められるか否かを判断するものとする。
ウ 被災者が、精神障害を発症し、引き続き業務に従事しなかった場合は、精神障害発症前おおむね6か月間に従事した業務を対象としてその間に被災者が遭遇した慢性及び急性の心理的負荷が、精神障害発症の原因となり得る「慢性及び急性の心理的負荷」と認められるか否かを判断するものとする。
エ 被災者が、精神障害を発症・増悪する前に遭遇した慢性及び急性の心理的負荷が複数存在する場合は、各心理的負荷を個別に評価するものではなく、その複数の心理的負荷を総合し、その全体の心理的負荷が、精神障害の発症・増悪の原因となり得る「慢性及び急性の心理的負荷と認められるか否かを判断するものとする。
オ 精神障害の発症・増悪には、労働者がその労働生活においてまれにしか遭遇しない非日常的な事件的出来事(ライフイベント)による急性の心理的負荷よりも、日常の労働生活おいて生ずるさまざまな混乱や落ち込み(デイリー・ハッスルズ)の「慢性の心理的負荷」が存在していることに留意するものとする。
カ 「慢性及び急性の心理的負荷」が認められるか否かは、個別事案毎に、被災者が精神障害を発症・増悪させる前の業務に従事することにより遭遇した慢性及び急性の心理的負荷を総合し、被災者の置かれた立場や状況を十分斟酌し、その全体の心理的負荷が、経験則上、被災者と同種労働者(職種、職場における地位や年令、経験等が類似する者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし、被災者の性格傾向が同種労働者の性格傾向として通常想定される者)を基準に判断するものとする。この判断において被災者の性格傾向が同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲をはずれるものでないかぎり、当該被災者を基準として差しつかえないものとする。
キ 自動車会社の設計業務に従事していた係長が、恒常的な時間外労働や残業規制による過密労働による慢性の心理負荷により精神的・肉体的に疲労を蓄積していたところ、二車種の設計出図期限がかさなり出図の遅れによる慢性の心理的負荷を受け、かつ労組職場委員長への就任により出図期限が遵守できなくなるとの不安・焦燥の急性の心理的負荷を受けた直後にうつ病を発症し、うつ病発症後の多忙な状況の下での作業調整による急性の心理的負荷及び南アフリカ共和国への出張命令による出図期限が遵守できなくなるのではないかとの不安・焦燥の心理的負荷は、これらを総合すると、前記評価方法により「慢性及び急性の心理的負荷」と判断されるものである。
ク [別表1]の「職場における心理的負荷評価表」は、前記「慢性及び急性の心理的負荷」と判断されるか否かの資料となるが、同表による心理的負荷の強度の評価方法は、被災者の置かれた立場や状況を十分に斟酌することなく、心理的負荷の強度を形式的に評価するものであり、本指針では採用しないものとする。
ケ 長時間の時間外労働(休日出勤を含む)による慢性の心理的負荷は、精神障害の発症・増悪と強い関連性があり、下記いずれかの場合は、この長時間労働単独で、精神障害を発症・増悪につき、要件1を満たすと評価するものとする。
- 発症・増悪前1か月間に100時間を超える時間外労働に従事していた場合
- 発症・増悪前2か月ないし6か月間に、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働に従事していた場合
3 判断要件2業務以外の心理的負荷について
被災者が、精神障害発症後業務に従事していた場合は業務に従事した最終日前おおむね1年間、被災者が精神障害発症後業務に従事していなかった場合は発症前おおむね6か月間に、被災者が遭遇した慢性及び急性の心理的につき、[別表2]の「職場以外の心理的負荷評価表」を参照し、被災者本人の置かれた立場や状況を十分斟酌し、その心理的負荷を総合して、全体として精神障害を発症・増悪させる原因となり得る心理的負荷の認められるか否かを判断するものとする。
4 判断要件3の個体側原因について
1精神障害の既往歴、2過去の生活史、3アルコール等依存状況、4性格傾向、の各事項につき、それらが精神障害の発症・増悪の確たる原因であるか否かを判断するものとする。
ただし、生活史を通じて、社会適応状況に特別の問題がなければ、確たる個体側要因はないものと判断する。
5 業務上外の判断について
前記判断要件による判断において、判断要件の1、2及び3の全てが判断されれば、精神障害の発症・増悪及びその精神障害による自殺は、「業務上」の疾病及び業務上」の死亡と判断するものとする。
法定利率・中間利息控除に関する意見書
法制審議会・民法(債権関係)部会 御中
幹事長 弁護士 川人 博
第1 中間利息控除の利率
- 中間利息控除の利率を5%とする改正案に反対である。
- 実際の金利水準に合わせていくべきであり,当面は1%程度とすべきである。
- 少なくとも法定利率を上回る利率には反対である。
第2 中間利息控除の計算方法
中間利息控除の計算方法は,法定利率の計算方法に合わせて単利(ホフマン方式)とすべきである。
第3 法定利率
法定利率を3%に引き下げる改正案に反対である。
第4 理由
- 当弁護団は,1988年10月に結成した弁護士の組織であり,過労死等の労災事件(企業損害賠償請求事件等)について,情報交換・経験交流や共同研究・共同行動を行い,もって,被災者・遺族の権利救済,過労死の予防を進めることを目的としている。
- 過労で重度の障害を負った人々,過労死で家族を失った人々,とりわけ一家の経済的支柱を失った遺族にとって,企業からの損害賠償金は経済生活を営んでいくうえで不可欠な金員である。したがって,その賠償金額が合理的に算出され補償されることは,被災者・遺族の権利救済にとって極めて重要な事項である。
かかる観点から見たとき,現行裁判実務において中間利息控除の基礎となる利率が5%とされ,実際の市場金利(1%弱)に比べて高く設定されていることは,被害者救済にとって大変マイナスとなっている。本来であれば,現在においては中間利息控除の利率は1%程度とすべきである。
したがって,今回の改正案において中間利息控除の利率を5%と定めることに強く反対する。
ましてや,法定利率を3%に下げ,他方,中間利息控除の利率は5%とするとの改正案は極めて合理性を欠き,被害者救済に重大な支障となる。 - 今回の改正案では中間利息控除の計算方法に直接触れていないが,ライプニッツ係数(複利)ではなくホフマン係数(単利)による計算方法と明示すべきである。けだし,法定利率が単利で計算されているのに,中間利息控除の利率が複利で計算されているのは損害額を不当に低くするものである。
- 過労死等の不法行為や債務不履行の賠償金支払を怠った企業等に対し,相当の遅延損害金を付加することは,加害者に対する制裁と被害者の救済の両面において重要である。かかる観点から見た場合,現行の法定利率5%を引き下げることは,加害者の責任を軽減し,被害者への補償を薄くする機能を果たすことになる。
以上
心理的負荷による精神障害の認定基準(発1226第1号 平成23年12月26日)「第5精神障害の悪化業務起因性」改定を求める意見書
下記PDFをご参照ください